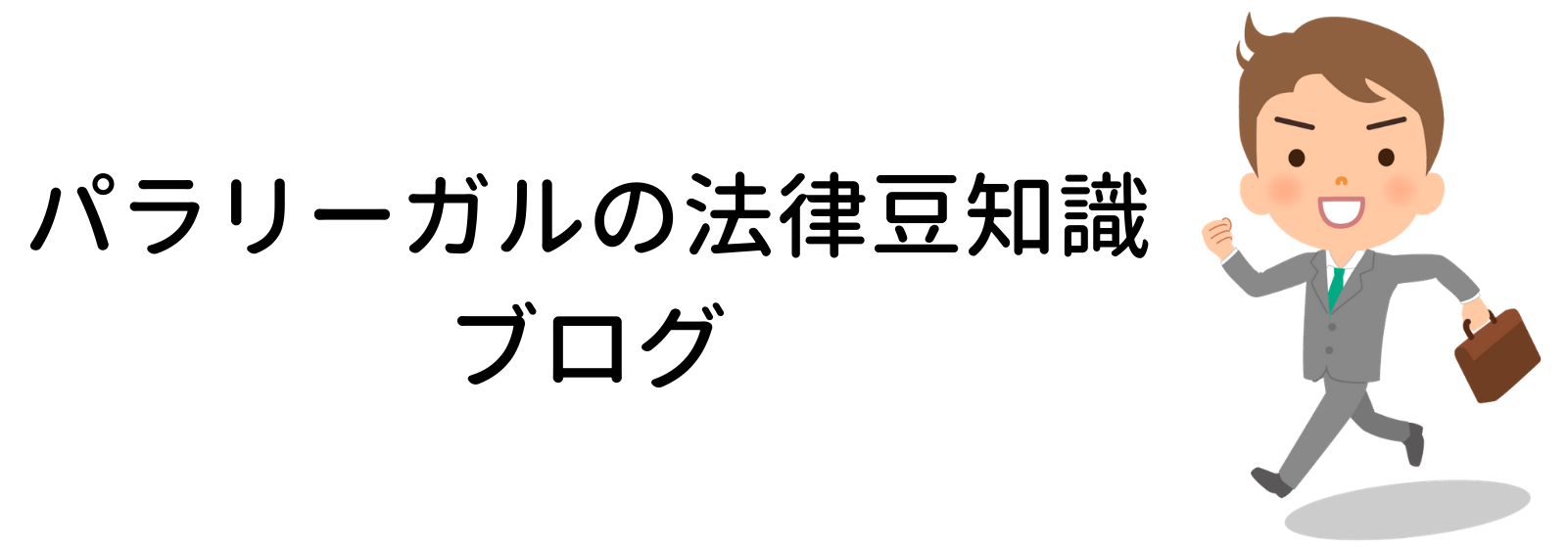マサトです。
相続放棄は、大抵は相続財産がマイナスの時に行います。
例えば、財産よりも借金の金額のほうが大きい場合などですね。
不動産があるならまだしも、借金などのマイナスの財産しかないのであれば、誰だって相続放棄を選択するはずです。
いつだって、相続人の自由意志で相続放棄を選択できます。
しかし、認知症の場合はその意思能力が問題となるのです。
本日は、認知症の場合の相続放棄についてお話しします。
「認知症でも相続放棄は可能ですか?」
「認知症の場合は、どのように相続放棄をすればいいですか?」
認知症の方は、単独で相続放棄をすることができません。
成年後見制度を利用する必要があります。
では、具体的にどのような点に注意して手続をすればいいのか。
以下、ご説明します。
相続放棄は法律行為

なぜ、認知症の場合は相続放棄をすることができないんですか?

相続放棄は法律行為です。意思能力がないと、法律行為を行うことはできません。
相続放棄は、財産を得る、または負債を免れるという重要な結果をもたらします。
法律行為に該当し、意思表示をすることで法律効果を発生させるものです。
認知症の場合は、意思表示に欠陥があるということになる可能性が高く、その場合は法律行為は無効になってしまいます。
つまり、相続放棄をしても無効となってしまうということです。
当然、遺産分割にも参加することはできません。
つまり、いつまでたっても相続手続が進まない状態が続いてしまうのです。
では、どうすればいいのでしょうか。
認知症の方が相続放棄をするには成年後見制度を利用する

認知症の人が相続放棄をするには、どうしたらいいのですか?

成年後見制度を利用すれば、成年後見人が相続放棄の手続を行ってくれます。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が著しく低下した人を保護するために、家庭裁判所に選任された成年後見人が本人の代わりに財産管理を行う制度です。
成年後見人がいれば、認知症の方の代わりに相続放棄の手続を行うことが可能です。
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。
費用も時間もかかってしまいますが、今後もずっと認知症の方の味方となってくれますので、安心できるはずです。
家族が成年後見人になったときは利益相反に注意

息子が成年後見人になったら、息子が代わりに相続放棄をしてくれるということですね?

利益相反となる場合は、息子さんでは相続放棄ができない可能性もあります。
成年後見人を選ぶのは、家庭裁判所です。
必ずしもなれるわけではありませんが、家族の誰かが成年後見人になることが多いです。
例えば、認知症の母親の成年後見人に長男がなるというかたちになります。
そのような場合に注意が必要なのが、利益相反です。
妻と子が相続人の場合、例でいうと母親と長男が相続人の場合、長男が母親の相続を自由にできてしまいますよね。
成年後見人として、母親には相続放棄をさせて、自分だけが相続できるようにするなど。
そういった、利益がぶつかり合う同士の状態を、利益相反といいます。
このような場合は、長男は母親の成年後見人として相続放棄はできません。
自分が相続放棄をした後に、母親の相続放棄をすることは可能です。
また、相続する場合には後見監督人か特別代理人が対応をします。
成年後見を利用するなら相続放棄の期間伸長をしておく

成年後見を利用する際の、注意点などはありますか?

成年後見の申立は時間がかかるので、相続放棄の3か月という期間に注意することが重要です。
相続放棄には、3か月という期間が決められています。
3か月を経過すると、単純承認をしたとみなされて、相続放棄をすることができなくなるのです。
詳しくは、こちらの記事をお読みください。
相続放棄には、相続人の調査や財産の調査が必要となりますので、ただでさえ時間がかかります。
その上、成年後見の申立までするとなると、3か月を経過してしまう可能性が高いんですね。
したがって、もし相続人の中に認知症の方がいて、成年後見の申立が必要であるならば、相続放棄の期間伸長の申立をするようにしてください。
まとめ
認知症というのは、あるとき急になるものではありません。
徐々に進行していくものです。
相続が発生してから動くのではなく、その前に成年後見の申立をしておくのが、安全策だと思います。
認知症の方の保護は、早いに越したことはありません。
結果的に、相続が発生した場合にも円滑に相続手続を行うことができます。