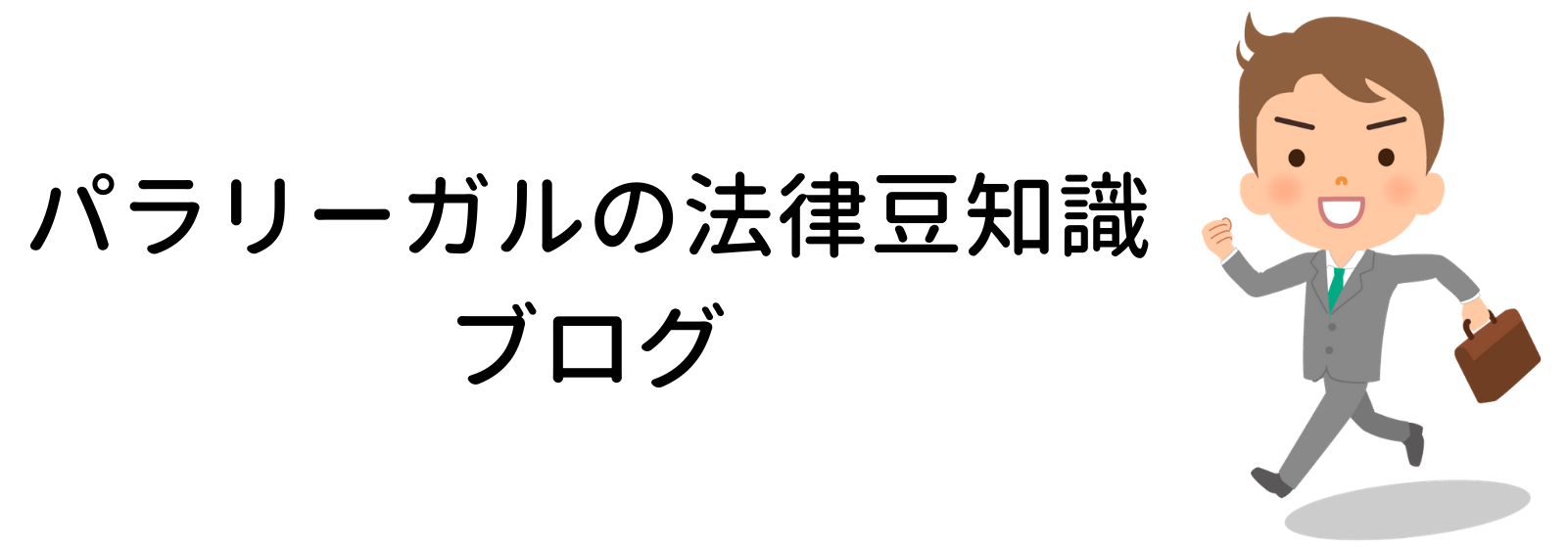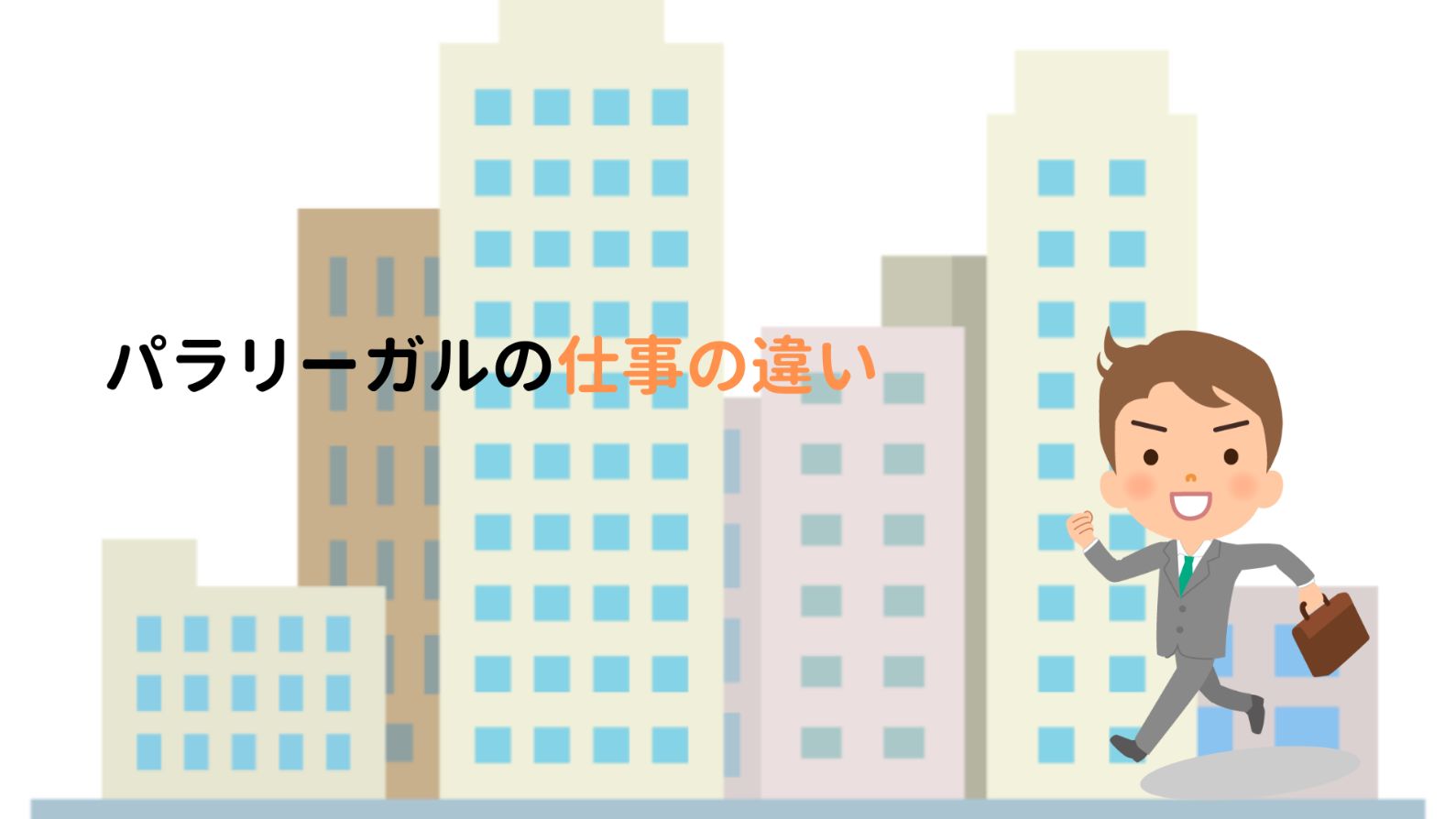マサトです。
法定相続人には、子が含まれます。
例えば、自分が死んだら自分の子供は必ず法定相続人です。
では、おなかの中にいる赤ちゃん、胎児はどのように扱われるのでしょうか。
本日は、胎児の相続についてお話しします。
「胎児も相続人になれるって聞いたけど、本当ですか?」
「相続人に胎児がいる場合の注意点などはありますか?」
胎児も相続人になります。
したがって、遺産分割協議や相続放棄をする際には、胎児のことも考えて行わなければなりません。
そのあたりが、胎児がいる場合の相続の注意点になります。
本記事では、胎児の相続について解説いたします。
胎児の相続で悩んでいるからは、参考にしてください。
胎児も相続人になれる?

胎児も相続人になれるって本当ですか?

本当です。民法でも、しっかりと明記されています。
胎児も相続人になります。
実は、民法ではっきりと明記されているのです。
民法886条に、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と。
そして、同条第2項では「胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」と規定されています。
つまり、胎児にも相続権はあるけれども、生まれてこなかった場合は当然相続権はないよ、という意味です。
相続権があるということは、相続分についても通常の子の法定相続分と変わりはありません。
法定相続分について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
では、胎児の相続の注意点はどういったことになるのでしょうか。
以下、ご説明いたします。
遺産分割協議は胎児が無事生まれるまで待つのが無難

胎児がいなくても、遺産分割協議は進められますよね?

胎児も相続人となるので、生まれるまでは遺産分割協議はしないようにしてください。
胎児がいる場合は、無事に生まれてくるまで遺産分割協議はしないほうがいいでしょう。
なぜなら、実際に生まれてくるまで相続人が確定しないからです。
また、出産前に胎児が死亡した場合と出産後に胎児が死亡した場合でも、相続人が変わってきます。
そのようなはっきりしない状況で遺産分割協議をしたとしても、後でやり直すこととなっては手間暇がもったいないです。
胎児が無事生まれたら、遺産分割協議を行います。
胎児が遺産分割協議に参加するためには、代理人を立てる必要があります。
母親は、相続放棄をしない限り利害関係人となるので、代理人にはなれません。
そうなると、特別代理人を立てることになります。
家庭裁判所に申立をして、特別代理人を選任してもらってください。
胎児も相続放棄はできる

胎児の相続放棄も可能ってことですか?

可能です。生まれてから、相続放棄をすることになります。
胎児が相続人になるということは、相続放棄もできるということになります。
相続放棄をするタイミングは、胎児が無事生まれてからです。
ただ、相続放棄をする場合も代理人を立てる必要があります。
母親が相続放棄をしていれば、母親が胎児の代理人となって相続放棄をすることが可能です。
母親が相続をする場合は、特別代理人を選任してもらって相続放棄をしなければなりません。
また、相続放棄には3か月という期間が設けられていますが、胎児の場合は生まれてから3か月で問題ありません。
相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
胎児は代襲相続も可能

代襲相続は、さすがに胎児には認められてないですよね?

代襲相続も認められています。
胎児に相続権が認められる以上、代襲相続をすることもできます。
代襲相続について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
父親が相続人になった場合ということですね。
例えば、胎児からみて父方の祖父が亡くなり、その時点で既に父親が亡くなっていれば、胎児が直系卑属として代襲相続をします。
胎児が相続人になることを気にしている人は、かなり少ないと思います。
代襲相続となれば、もっと少なくなることでしょう。
知らずに進めると、後々手続が面倒になるので、代襲相続についても注意が必要です。
まとめ
胎児が相続人になるというのは、意外だと思う方もいるでしょう。
しかし、もし胎児が相続人にはなれないとしたらどうなると思いますか?
被相続人が亡くなった直後に生まれた子には、相続権がないということになります。
それが、紙一重のタイミングであったとしてもです。
そのような事態を避けるためにも、胎児には相続権が認められるべきです。
相続が発生した時には、胎児のことも想定して相続手続を進めるようにしてください。