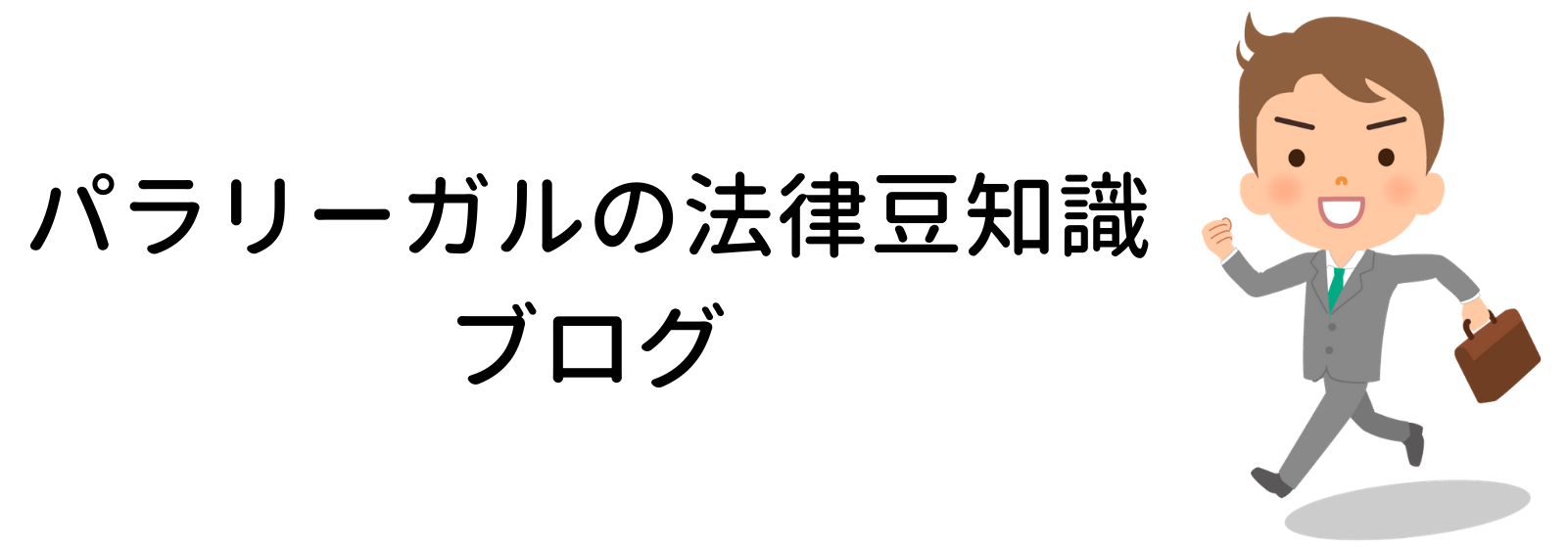こんにちわ、マサトです。
雪とコロナの影響で、街にはあまり人がいなかったみたいですね。
東京都の感染者数は、また更新したみたいですし、どこまで猛威をふるうのでしょうか。
何よりショックだったのは、志村けんさんがお亡くなりになったことです。
一ファンとして、大変ショックを受けました。
心より、ご冥福をお祈りいたします。
コロナによりお亡くなりになる方が出る中で、自分がもし感染したときのことを想像してみました。
私も持病を持っているので、重症化するリスクは無視できません。
コロナだけでなく、人生はいつ何があるかわからないものです。
そう考えると、遺言書を作っておくことは、やっぱり大切だなと思いました。
仕事柄、遺言書に触れることが多いですが、あるとないでは亡くなった後の状況が大きく変わります。
「遺言書ってどうやって作ったらいいの?」
「遺言書には何を書けばいいんだろう。」
本日は、そういった疑問をお持ちの方に遺言書の書き方について解説しますので、参考にしていただければと思います。
まずは家族に伝えたいことを考える

遺言書って何を書いたらいいんですか?

遺言書には、財産だけではなく家族に伝えたいことを書くこともできます。
遺言書は、なんのために残すと思いますか?
自分の死後、財産をだれに分けるのかを明確にし、家族が揉めないようにするため。
そう思っている方が多いと思います。
それ自体は間違っていないのですが、そのベースとなる想いがあるはずです。
なぜその財産を特定の人に残したいのか、それをまずは考えてみてください。
もっと言えば、財産のことは別として家族に伝えたいことだけを考えてみてください。
そして、伝えたいことが明確になったら、それを手紙のように文章にします。
それを、そのまま遺言書に記載するのです。
「遺言書に、家族に伝えたいことなんて書いていいの?」、と思うかもしれませんが、書いていいのです。
むしろ、書くべきです。
財産のことだけ記載すると、家族にはなぜそのように分けたのか、理由がわかりません。
ある程度は想像できるでしょうが、あくまでも想像でしかないです。
その結果、家族間で揉め事が発生したりします。
遺言書の書き方で大事なのは、「家族へ伝えること」と「財産の分け方」をセットで記載することなのです。
なので、まずは家族へ伝えたいことを考えて、まとめておくことがスタートになります。
財産を一覧にして分け方を決める

財産がいくつかあるけど、全部手書きで書かないといけないの?

法改正があり、財産目録は手書きじゃなくてもよくなりました。
財産を一覧にする
財産は、少なくても一覧にまとめておくことをおすすめします。
少ないとはいえ、通帳などは複数持っている人が多いでしょうし、一覧にしておかないと抜け漏れも発生してしまいます。
また、借金などがあればそれも一覧に記載しておいてください。
借金も、マイナスの財産となります。
一覧にするときは、詳細についても記載します。
例えば、不動産であれば地番や家屋番号、口座であれば支店や口座番号などです。
不動産登記簿謄本や通帳があればわかるのですが、どちらにせよ必要になるので詳細まで記載しておきましょう。
財産の一覧が完成したと思います。
これがそのまま、「財産目録」となります。
これまでは、自筆で遺言書を作成する際はこの「財産目録」も手書きで書く必要がありました。
しかし、法改正によって手書きじゃなくてもよいことになったので、作成した「財産目録」をそのまま使用します。
財産の分け方を決める
ここまでの作業が完了したら、分け方を決めます。
先ほど、家族へ伝えたいことを考えているので、ある程度方向性も決まっていると思います。
例えば、長男は家業を継いでくれたからこの財産を、長女は身の回りの世話をしてくれたからこの財産を、というように具体的に決めていってください。
これまでのことをすべて文章におこしたら、遺言書の完成です。
ただ、遺言書には3つの種類があります。
次のステップで解説しますので、自分に合った方法を選択してください。
遺言書の形式を決める

遺言書って自分で書くしかないの?

自分で書く以外にも方法はありますよ。
遺言書には、3つの種類があります。
それぞれ特徴がありますので、以下で説明します。
自筆証書遺言
もっとも簡易な方法です。
自分で紙に書いて残すという方法ですね。
メリットは、いつでもどこでも作成することができる点です。
また、お金もかかりません。
デメリットは、内容に間違いなどがあると効果を発揮できなくなることです。
せっかく書いた遺言書が、無駄になってしまうリスクがあります。
また、ちゃんと保管しておかないと失くしてしまうリスクもありますね。
しっかり調べた上で、自信をもって作成できる場合は、自筆証書遺言でも問題ないかと思います。
公正証書遺言
もっとも確実な方法です。
なぜなら、公証役場で公証人が聞き取りをして作成するからです。
メリットは、やはりその確実性です。
公証人が作成するので、間違うという可能性もありませんし、公証役場で遺言書が保管されるので、失くしてしまうリスクもありません。
デメリットは、手間と費用がかかることです。
公証役場とのやり取りが発生しますし、数万円ほどの費用がかかってしまいます。
とはいえ、総合的に考えると最も確実な方法となるので、公正証書遺言での作成を強くおすすめします。
秘密証書遺言
あまり使われない方法です。
公証役場に行くのは公正証書遺言と変わらないのですが、公証人は中身を全く知りません。
遺言があるということを証明してくれるだけです。
メリットは、名称のとおり遺言の中身を秘密にしておけることです。
デメリットは、自筆証書遺言と同じで、内容に不備がある場合のリスクと、紛失のリスクがあることですね。
以上、遺言書の3つの種類に説明しました。
注意点としては、公正証書遺言以外は遺言書を発見したら家庭裁判所の検認が必要になることです。
勝手に開けてはいけませんよということですね。
そういった意味でも、公正証書遺言が最も確実な方法だと思います。
まとめ
本日は、遺言書について簡単に解説しました。
人生、いつ何があるかわかりません。
家族のためにできることを考えて、行動してみてください。
とりあえず、自筆でもWordでもいいので書いてみるというのもありだと思います。
考えもまとまりますし、作成したものはあとで公正証書遺言を作るときに役立ちます。
遺言書の書き方は、まずは家族への想いです。
そのことを頭の片隅に置いておいてください。