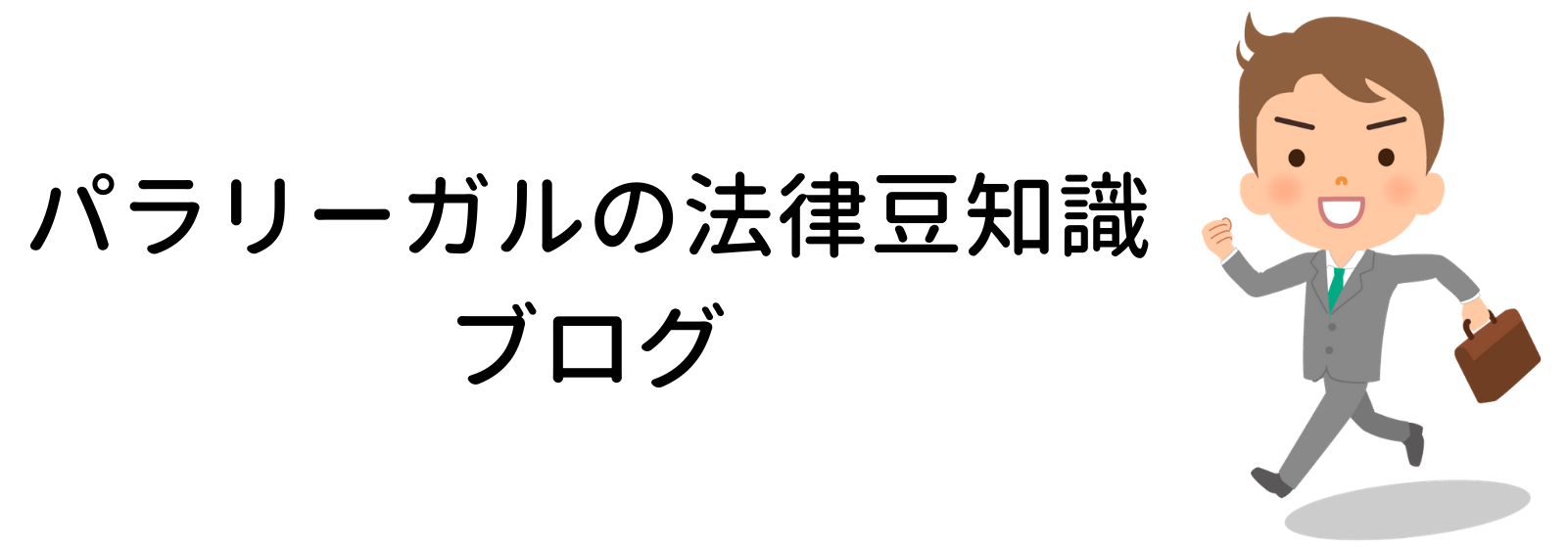マサトです。
ペットは、家族の一員です。
犬でも猫でも、トカゲや魚であっても、愛情を注いできたペットは家族同然の存在だと思います。
私も犬を飼っていますが、結婚前から一緒にいるので家族の誰よりも長い時間を過ごしてきたことになりますね。
そのような家族同然のペットは、自分の死後どうなるのだろうと考えたことはありますか?
家族がいれば、おそらく飼い続けてくれることでしょう。
しかし、独り身だったらどうでしょう。
また、ペットがトカゲや蛇といった特殊な動物だった場合、爬虫類嫌いの家族だとしたら飼い続けてくれるでしょうか。
本日は、ペットの相続についてお話しします。
「ペットに相続させることはできるの?」
「死後、ペットを安心して任せられる方法はあるの?」
家族同然のペットに、今後も生き続けられるよう財産を残しておきたいと考えるのはおかしなことではありません。
それくらいの愛情をもっているからこそ、死後のペットの安否が心配になるのです。
本記事では、ペットの相続について詳しく解説します。
ペットのことが心配な方は、参考にしてください。
相続におけるペットの取り扱い

そもそも、ペットは法律上どのように扱われているのですか?

法律上は、「物」として扱われます。
冒頭でもお伝えした通り、愛情を注いできたペットは家族同然の存在です。
恋人や友達と同じような存在に感じていると思います。
しかし、ペットは人ではありません。
法律上は、残念ながらあくまでも「物」として扱われます。
したがって、ペットに相続財産を相続させるということはできないのです。
仮に相続させることが可能であったとしても、ペットは自分で財産を処分することはできません。
結局は、誰か人が介在しないとペットは生きていくことができないのです。
では、ペットを守るためには具体的にどのような方法があるのでしょうか。
相続時にペットを守る方法

ペットを守るためには、どういった方法があるのですか?

方法としては、2つあります。
相続時にペットを守る方法は、大きく分けて2つあります。
どちらも、内容的には一緒ですが方法が異なります。
負担付遺贈でペットを守る
負担付遺贈とは、遺言書で条件を指定して財産を相続させることです。
つまり、財産を渡す代わりにペットの面倒を最後まで見てくれという内容の遺言書を作成し、その通りにしてもらうということですね。
その約束が履行されなかったら、遺贈はなかったことになります。
遺言書については、こちらの記事をお読みください。
負担付死因贈与でペットを守る
負担付死因贈与とは、条件を指定して死亡したタイミングで財産を譲り渡すことです。
負担付遺贈を全く同じ効果がありますが、遺言書で指定するのではなく、契約でその内容を実現するということですね。
ペットを守るために重要なこと

負担付遺贈か負担付死因贈与をすれば、安心して任せられるでしょうか?

手段としてはこの2つですが、最も大切なのは誰にお願いするのかということです。
負担付遺贈でも負担付死因贈与でも、財産をあげる代わりに大切なペットを育ててもらうことをお願いするというのは変わりません。
お金をもらっているわけですから、約束を無下にするようなことはないと思います。
しかし、完全に安心できるかというと、そんなことはありませんよね?
私なら安心できません。
負担付遺贈も負担付死因贈与も、あくまでも手段です。
最も大事なのは、誰が飼ってくれるのかという点だと思います。
当然、動物が好きな人じゃないと任せられませんよね。
また、自分と同じように大切に育ててくれるという信頼も必要です。
つまり、自分の死後ペットを守るために最も重要なことは、安心して育ててくれると思える相手を見つけることです。
そういう人さえ見つけられれば、あとは負担付遺贈が負担付死因贈与で正式にお願いするだけです。
ペットの相続で気を付けること

ペットの相続で気を付けることはありますか?

ペットは「物」ですので、相続財産となるのが注意点です。
法律上、ペットは「物」であるとお伝えしました。
つまりそれは、相続財産となりえるということです。
最近では、血統書付きの犬や猫は高額で取引されています。
また、爬虫類なども種類によっては100万円を超えてきます。
相続人の中には、換価してお金にしたいと思う人がいてもおかしくありません。
そういった相続財産全体のことを考慮して、ペットのことを考える必要があります。
場合によっては、ペットの価値分の財産を穴埋めする必要も出てくるかもしれません。
まとめ
ほとんどのペットは、人間がいないと生きていくことができません。
自分が死んで、他に誰も育てる人がいなければ、それはペットの死でもあるのです。
一度飼った以上、自分が死んだ後のことまで考えてあげることが、飼い主としての責任だと思います。
まずは、家族や親せき、友人など身近な人で、安心して任せられる人を見つけてください。
そして見つかったら、法律的な筋を通してお願いするようにしましょう。