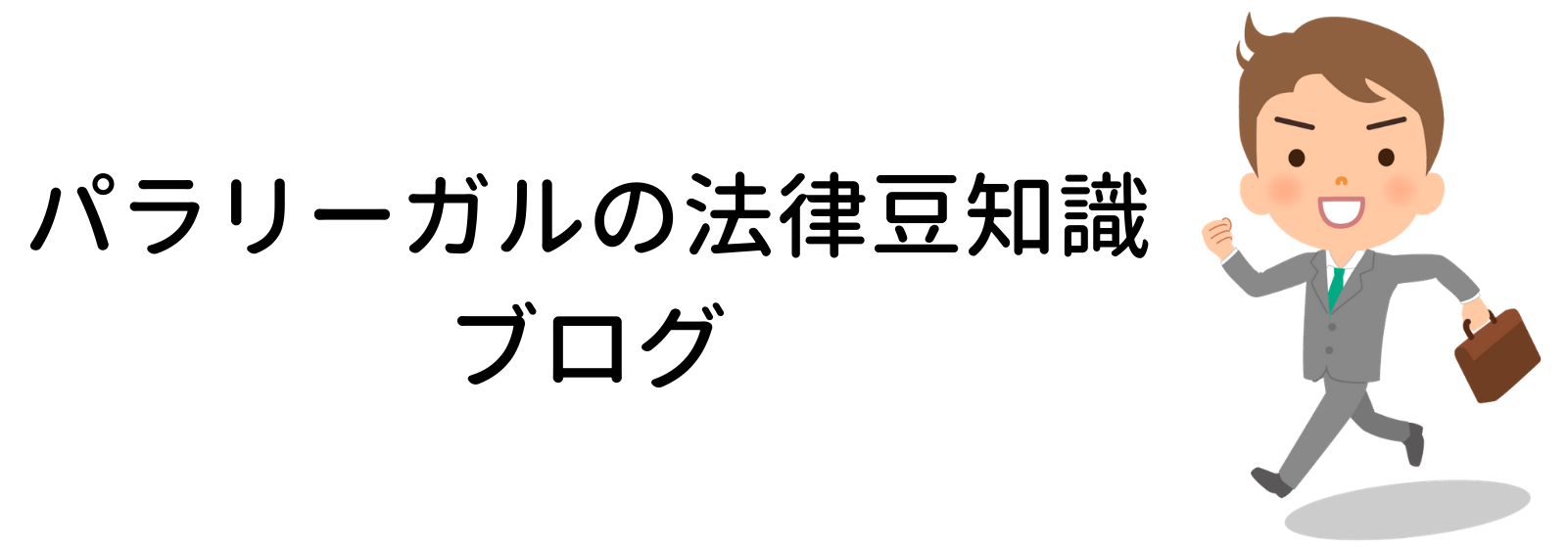相続が発生した際、現金や不動産などの相続財産のことはすぐにイメージできると思います。
相続財産をどのように分けるのかは、相続において非常に重要なことです。
どうしても、そこに目がいってしまうのは仕方がありません。
しかし、相続財産と同様に重要なこともあるのです。
それが、祭祀財産です。
本日は、祭祀財産についてお話しします。
「祭祀財産ってなんですか?」
「祭祀財産は、相続財産ではないんですか?」
祭祀財産とは、家系図や仏壇、お墓、遺骨などのことです。
祭祀財産は、相続財産とは異なる財産となります。
したがって、相続財産のように遺産分割の対象とはならず、原則相続税の対象にもなりません。
では、祭祀財産はどんな財産で誰が承継するのか、以下ご説明します。
祭祀財産は相続財産ではない

祭祀財産は、相続財産ではないのですか?

相続財産とは違います。相続税の対象にもなりません。
祭祀財産とは、家系図や仏壇、お墓、遺骨であるとお伝えしました。
言うなれば、先祖などを祀るためのものです。
相続財産であれば、相続人間で分けるのが普通ですよね?
しかし、祭祀財産を相続財産のように分けてしまっては、祭祀の際にいろいろと面倒になります。
なので、祭祀財産は相続財産とは区別されているのです。
祭祀財産は祭祀承継者が引き継ぐ

相続財産でないなら、祭祀財産は誰が引き継ぐのですか?

実は、祭祀財産を誰が引き継ぐのかは、民法に定めがあります。
祭祀財産は、葬儀などを代表する人が承継します。
祭祀主宰者といいますが、祭祀主宰者がイコール祭祀承継者のことです。
祭祀承継者は、民法で決め方が規定されています。
昔は、長男が祭祀承継者となるのが当たり前でしたが、今は違います。
まずは、被相続人が祭祀承継者を指定している場合です。
その場合は、被相続人が指定した者が祭祀承継者となります。
指定の方法は、生前に口頭で指定してもいいですし、遺言書での指定も可能です。
被相続人の指定がない場合は、その家の慣習に従います。
代々、長男が祭祀財産を引き継ぐのが慣習であれば、長男が祭祀承継者となるのです。
そして、被相続人の指定もなく、慣習も特にないような場合は、家庭裁判所が祭祀承継者を決めます。
家庭裁判所が祭祀財産を承継する者を決める時は、被相続人との関係性や利害関係人の意見などを総合的に考慮して、最終的に祭祀承継者を決定します。
祭祀承継者は拒否できない

祭祀財産を引き継ぎたくない場合は、断れるんですか?

原則、祭祀財産を引き継ぐことは拒否できません。
祭祀財産を承継する祭祀承継者となった場合は、原則拒否することができません。
相続財産は相続放棄をすることができますが、祭祀財産を承継する場合は放棄できないのです。
相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
ただ、祭祀財産をどう取り扱うのかは、祭祀承継者が決めることができます。
誰かに、祭祀財産の管理を強要されることもありませんし、祭祀財産を処分することだって可能です。
祭祀財産が処分されてしまった場合には、相続人間でトラブルとなる可能性もあるので、祭祀財産を誰に承継させるのかは、慎重に決めたほうがいいでしょう。
まとめ
祭祀財産の維持・管理には、費用がかかります。
また、祭祀財産を承継したからといって、相続財産の分配で優遇されることもありません。
そういったことをふまえて、祭祀財産を承継する人を選ぶ必要があります。
祭祀財産を承継した人は、祭祀財産を自由に処分することが可能です。
勝手に処分されてトラブルにならないよう、祭祀財産を承継する人は慎重に決めるようにしましょう。