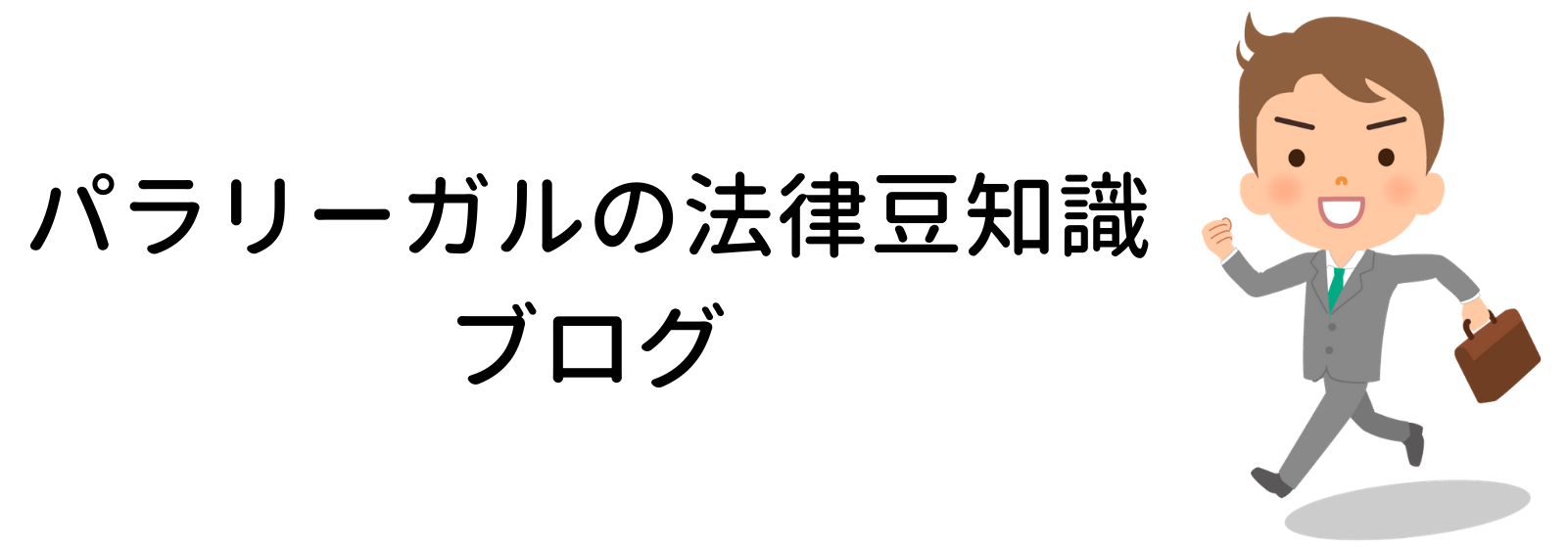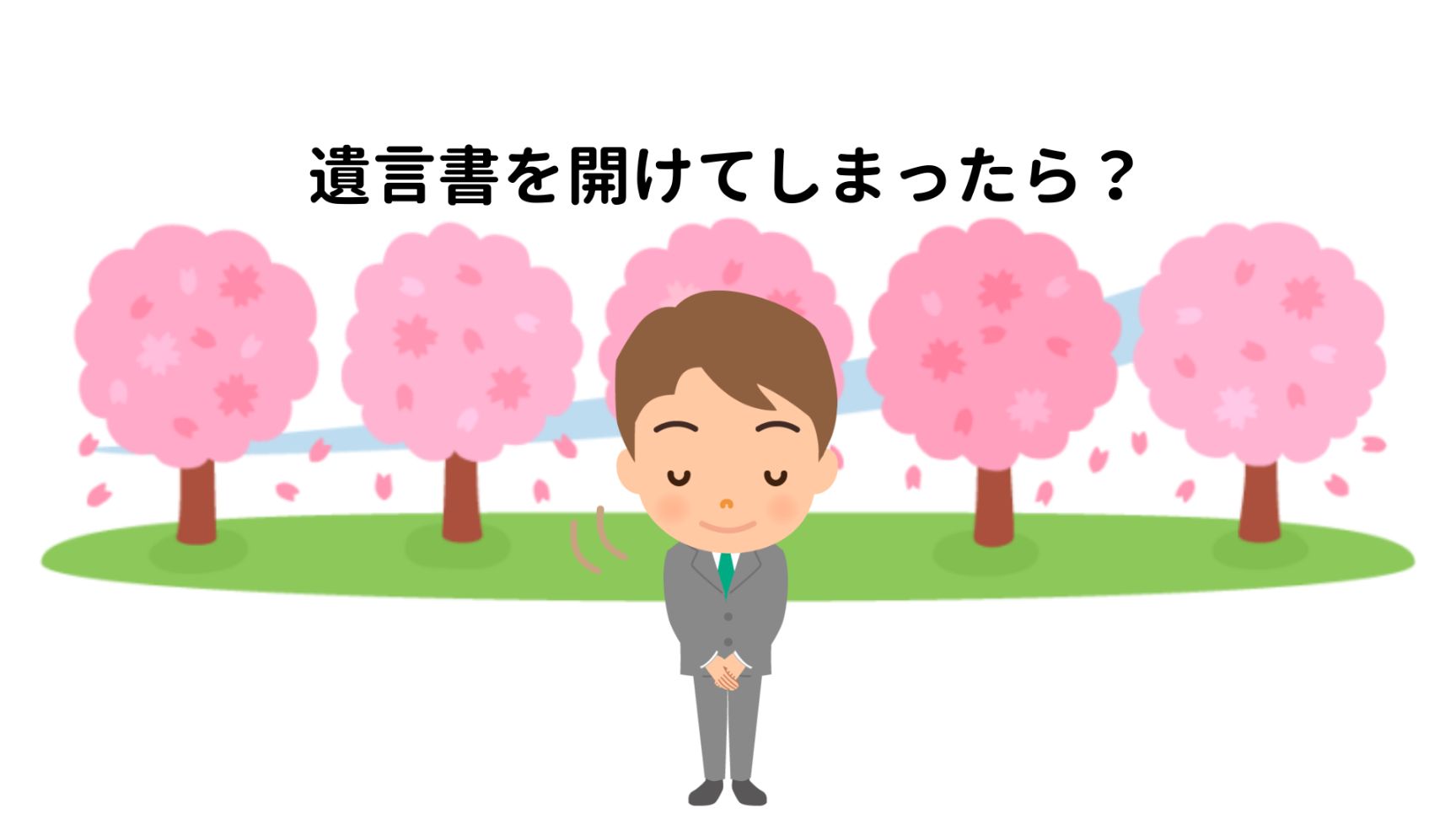マサトです。
一般の企業であれば、部の中に課があり、係に分かれていたりします。
そして、係長や主任がいて、課長がいて部長がいる。
そういう組織構成になっているのが、普通です。
では、法律事務所はどうなのでしょうか。
もちろん、同じような組織構成になっています。
本日は、パラリーガルの管理職の仕事についてお話しします。
「パラリーガルにも管理職っているの?」
「パラリーガルの管理職って、どんな仕事をしてるの?」
パラリーガルにも管理職がいます。
管理職の場合は、事件処理をすることは基本的にありません。
パラリーガルでありながら、パラリーガルの主要業務である法律事務をしていないということです。
本記事では、パラリーガルの管理職の仕事について詳しく解説します。
パラリーガルの仕事に興味がある方は、参考にしてください。
パラリーガルの組織構成
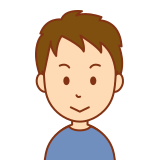
法律事務所って、部とか課とかに分かれてるんですか?

完全に事務所によりますが、パラリーガルが20人以上いたらほぼ間違いなく分かれているでしょう。
パラリーガルの組織構成は、法律事務所によって違います。
弁護士一人、事務員一人であれば、組織構成も何もありません。
ただ、もし弁護士一人、事務員一人の事務所であったとしても、部長という役割を与えられているのだとしたら、その役割が求められているということです。
逆に、パラリーガルが何十人いても全員がパラリーガルとしての役割しか求められていないのであれば、管理職はいらないということです。
事務所の規模や考え方によって、法律事務所の組織構成は全く違うものになります。
自分の描いているキャリアと乖離しない事務所で働くことが、大切です。
基本的には、パラリーガルが少ない事務所では組織化されておらず、パラリーガルが多い事務所では組織化されていると考えてもらって大丈夫です。
では、組織化されている事務所の管理職の業務は、どんなものでしょうか。
以下、標準的な役割をご説明します。
係長は現場のパラリーガルのリーダー
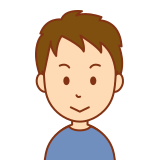
パラリーガルに係長っているんですか?

係長までいるのは珍しいですが、規模が大きければいます。
係長、主任、チームリーダーといった呼び名だと思います。
役割としては、現場のリーダー的存在です。
現場のリーダー的存在なので、必然的に業務経験が長いパラリーガルが係長になることが多くなります。
現在の業務量やスタッフの習熟度などを、最も把握しているのが係長です。
したがって、業務改善などの際には係長が中心となって現場の意見をまとめて、課長に報告したりします。
パラリーガルの業務改善については、こちらの記事をお読みください。
また、課長を補佐する役割もあります。
課の人数が多いと、課長も全体をみることができません。
そういったときに、係長がサポートしてあげることで、課長の管理業務を軽減することができます。
課長はパラリーガル業務とは原則無縁
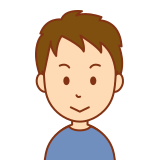
パラリーガルの課長って、やはり経験が長い人がなるんですか?

そんなことはありません。パラリーガルの適性と、課長の適性は全く別です。
課長の役割は、課の生産性を高めることです。
パラリーガルの場合、売り上げが目標になることはあまりありません。
処理件数が目標になることが多いです。
つまり、課員の処理件数をどれだけ伸ばすことができるのかが、課長に求められる役割になります。
そのために、業務改善やリソース配分、課員のモチベーション管理といったことを行うのです。
パラリーガルの場合、売り上げや処理件数といった数値的な意識が低いことが多いです。
どちらかというと、依頼者のためにというマインドのほうに寄ってしまいます。
そういう意味では、パラリーガルとして専門性を高めていきたいと考えている人は、課長に向いていません。
実際、パラリーガルとして経験が長いという理由で、課長に選ばれることは少ないです。
法律事務所も一つの企業ですので、利益を上げなくてはなりません。
パラリーガルとして専門性を高めるのはもちろん重要ですが、それ以前に利益を上げるという考え方がないと、法律事務所の課長は務まらないのです。
パラリーガルの管理職を目指している方は、利益の部分を意識して仕事をするようにしてみましょう。
部長は経営層に近い
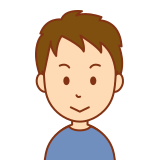
部長になっても、パラリーガルなんですか?

パラリーガルには違いありませんが、実務をしないという意味では確かに違和感はありますよね。
部長の役割は、部全体の生産性を高めることと、先のことを考えることです。
課長は、課の生産性を高めるのが役割ですよね。
しかし、課の生産性が上がったとしても、他にそのしわ寄せがいってしまい、事務所全体で見たときに生産性が下がってしまうということがあります。
課長は役割を果たしているだけなのでそれでいいですが、部長は全体を見なくてはなりません。
事務所全体で見たときに生産性が下がるのであれば、そういった選択はしないということになるのです。
もちろん、あえてそういった選択をするときもありますが、いずれにせよ部長は事務所全体のことを考えて判断することが求められます。
課長と決定的に違うのが、将来を見据えて考えなくてはならない点です。
課長は、現在から半年先、せいぜい1年先くらいを見ています。
しかし、部長は2年先、3年先の受任数や処理件数、生産性、人員数、部署構成、売り上げなどを見て、経営の部分まで関わっていきます。
部長までいくと、ほぼ法律事務をすることはなくなります。
法律事務がしたいという方は、せいぜい課長まででしょうね。
課長であれば、プレイングマネージャーとして法律事務をしながら管理職をすることも可能です。
まとめ
法律事務所にも、管理職というのは必要です。
個々が、パラリーガルとして専門性を高めて職人のようにやっていくのも、悪いとは思いません。
しかし、そうなると中々業務改善など全体で生産性を上げていくことが難しくなります。
また、各々が見ている方向も異なってしまいます。
管理職という役割を置くことで、チームとして同じ方向進んでいくことができるようになるのです。
パラリーガルとして専門性を高めていきたいのか、パラリーガルの生産性を高めていく管理職になりたいのか、進みたい道を決めて法律事務所を選んでみてください。