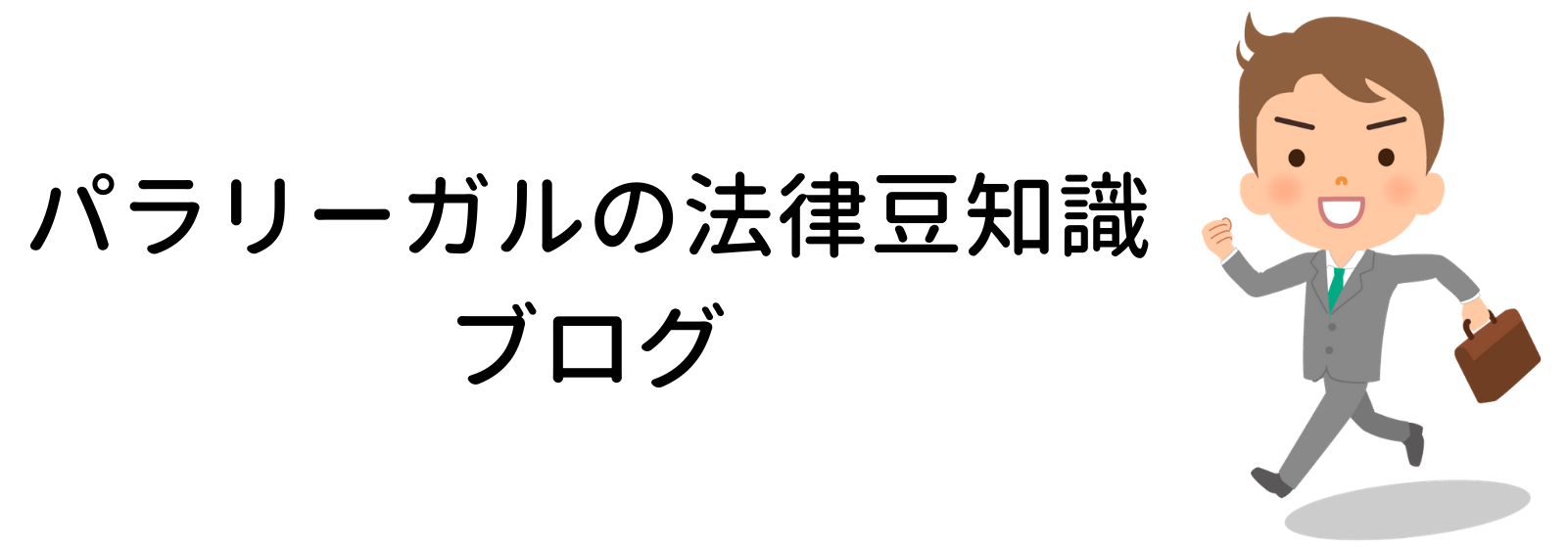どうも、マサトです。
コロナの影響はとどまるところを知らず、毎日感染者の数が増加していますね。
政府は、現金給付を決定したようですが、それで解決できないケースも多くあるでしょう。
債務整理を検討される方も、まだまだ増えるかと思われます。
本日は、自己破産の手続についてご説明いたします。
「自己破産って聞くと、それだけで不安になります…。」
「本当に借金がなくなるんですか?」
そのような不安を抱かなくても大丈夫です。
自己破産とは、すべてリセットすることが目的なのではなく、すべてリセットして再スタートをしてもらうようにすることが本当の目的です。
実際に、申立をした人の約97%は免責許可がおりているのです。
この記事では、実際の自己破産の手続の流れや注意点などを解説します。
この記事を読んでいただければ、自己破産の手続の流れを理解し、安心して専門家に依頼ができるようになります。
自己破産とは
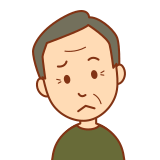
自己破産の手続について教えてください。

自己破産は、裁判所に申立をして借金をゼロにする手続です。
自己破産とは、一言でいえば借金を免除してもらう手続です。
裁判所に申立を行い、「免責許可決定」をもらうことで免除となります。
自己破産の手続は2種類
自己破産の手続は2つあり、配当できるような財産がなければ同時廃止事件、配当できる財産があれば管財事件となります。
同時廃止事件は、配当すべき財産がないという前提で進むので、管財事件に比べて短期間で手続が完了します。
また、専門家の報酬も管財事件より安いのが通常ですし、管財人という財産を処分する者がつかないのでその分の費用もかかりません。
同時廃止事件と比べて管財事件は、時間もお金もかかります。
また、管財人がつくことで、自己破産の手続期間中は申立人宛の郵便物がすべて管財人を経由して届くことになります。
同時廃止事件で進むのなら、それに越したことはありません。
しかし、同時廃止事件で申立をしたとしても、どちらにするのかは裁判所の判断になりますので、管財事件になる可能性も大いにあります。
原則は管財事件なので、基本的には管財事件になるだろうと思っておきましょう。
自己破産の手続開始原因
自己破産の手続をするためには、「支払不能」となっていることが必要です。
「支払不能」とは、簡単に言うと返済ができない状況のことです。
返済日がきても全く返せない、一部は返せるけど借金は増える一方だ、という状況ですね。
当然ですが、毎月浪費などでお金を使っていて、そのせいで返済に充てるお金がありませんというのは、通用しません。
浪費をやめれば返済できるわけですから。
自己破産できない場合(免責不許可事由)
自己破産の手続ができない場合というのがあります。
破産法に規定されているのですが、その中でよくあるケースを3つ挙げておきます。
- 浪費
- 賭博
- 株やFX取引
この3つが原因で借金が膨らんでしまった場合は、免責を許可しませんと破産法に規定されているのです。
上記以外は、破産法252条をご確認ください。
しかし、ご安心ください。
これに該当したからといって、絶対に免責がおりないわけではないのです。
「裁量免責」といって、裁判所が諸々の事情を考慮して免責するのが相当だと判断する場合があります。
よほど悪質な場合ではない限り、「裁量免責」がおりることのほうが圧倒的に多いです。
ただし、依頼した法律事務所によっては経験値が少なく、裁量免責までもっていけない可能性もあります。
実績のある法律事務所に依頼するようにしましょう。
今すぐに自己破産で借金をゼロにしたい方は、こちらの記事をお読みください。
資格制限
いわゆる資格制限というもので、破産の申立から免責がおりるまでの期間、業務を行うことができなくなる仕事があります。
資格を失うわけではありません。
代表的なものは以下の3つです。
- 弁護士や司法書士などの士業
- 警備員
- 生命保険募集人
これらの職業に就いているかたは、申立から免責が確定する間、約3か月から半年ほどは仕事ができなくなります。
それを避けるために、自己破産を断念される方も多いです。
その場合は、任意整理か個人再生の手続を行うしかありません。
具体的な手続の詳細を知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
自己破産の手続の流れ
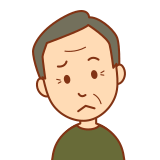
自己破産の手続って面倒なんですか?

書類収集が大変ですが、借金をゼロにするためなのでご自身の努力も必要です。
自己破産の手続で最も大変な作業は、申立書を作成するための準備です。
借金を免除するわけですから、裁判所には家計の状況や財産関係のことをきっちり報告する必要があります。
途中までの流れは、債務整理の他の手続と一緒になります。
債権調査までの手続の流れを知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
【自己破産の手続の流れ①】必要書類の収集
自己破産の手続では、色々な書類が必要となります。
ケースによっても異なりますので、以下代表的なものをご説明します。
- 住民票
- 居住証明書(賃貸契約書など)
- 申立に至った事情
- 給与明細(原則2か月分)
- 源泉徴収票
- 家計収支表(原則2か月分)
- 退職金がわかる書面
- 通帳
- 保険証券
ざっとですが、これだけあります。
財産関係で、他に車などがあれば車検証や査定書も必要になります。
この書類収集で挫折してしまう方も多いです。
申立までは、ある程度の時間がかかります。
その間、毎月家計収支表や給与明細を依頼した専門家に提出しなければなりません。
通帳などは、専門家に預ければ記帳してコピーをとってくれますが、事務所によっては依頼後に記帳があった分は自分でとってくださいというところもあります。
申立に至った事情についても、自分で書いてくださいという事務所もあれば、30分ほど時間をとって電話で聞き取るという事務所もあります。
どれも比較的簡単に取れる書類ではありますが、種類が多いですし継続して提出しなければならないので、意外と大変なのです。
しかし、自己破産の手続を進めるためには絶対に必要な書類になるので、諦めずに頑張りましょう。
【自己破産の手続の流れ②】債務者審尋
申立をすると、一番最初に行われます。
裁判所に行って、裁判官が事情などを聞き取る工程です。
裁判所によって運用が異なっており、例えば東京であれば即日面接という制度があるので、債務者審尋はありません。
裁判所によっては審尋に行かなければならないので、その時間が必要になります。
審尋が終わると、自己破産手続きの開始決定が出ます。
同時廃止事件の場合は、【自己破産手続きの流れ⑤】まで飛びます。
管財人面談と債権者集会はありません。
【自己破産の手続の流れ③】管財人面談
管財事件の場合は、管財人がつきます。
そして、管財人との面談が必要になるのです。
質問内容は、借入に至った原因や収入、財産の話など一般的な質問になります。
それ以外は、管財人が気になったことなどを聞かれるだけです。
弁護士に依頼した場合は、基本的に同行してくれるのであまり考えこまないでも大丈夫です。
【自己破産の手続の流れ④】債権者集会
債権者集会では、自己破産の手続の進捗を報告し、債権者の意見を聞きます。
通常であれば、1回目の時点で財産の調査も終わっており、債権者もあまり出席することはないので、配当する財産があれば配当となって終了です。
債権者集会にも出席する必要があるので、そのための時間を確保してください。
【自己破産の手続の流れ⑤】免責審尋
債務者審尋と同様に、裁判所によって運用が異なります。
東京地裁の場合は、必ず免責審尋を行います。
ただし、管財事件の場合は債権者集会と同日に行いますので、別日に出廷する必要はありません。
以上が、自己破産手続きの流れです。
裁判所によって運用は異なりますが、基本的には上記の流れで進んでいきます。
同時廃止の場合は3か月ほど、管財事件の場合は半年ほどで終わるのが通常です。
自己破産の手続で注意すべきこと
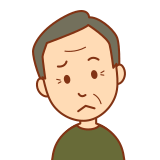
知人への返済だけはしたいのですが・・・。

返済は絶対にしないでください。
自己破産の手続で、絶対にやってはいけないことが2つあります。
- お金の貸し借りをすること
- 財産などを隠すこと
当たり前のことではありますが、意外とやってしまう方が多いのです。
家族や知人との貸し借りであれば大丈夫だろうと思ってしまうようですが、家族や知人であってもいけません。
申立に必要な書類の中に、通帳があります。
通帳には、原則すべてのお金の流れが記載されています。
少しでも不自然な点があれば、すぐにばれてしまいますので絶対にお金の貸し借りや財産を隠すことはしないようにしてください。
まとめ/自己破産の手続は書類収集が重要
自己破産の手続は、専門家に依頼すればすべてやってくれます。
しかし、申立に必要な書類のほとんどは自分で収集しなければなりません。
自己破産の手続においては、書類収集がネックなのです。
書類収集がスムーズにできれば、それだけ手続も早く終わります。
逆に、書類収集ができないと代理人から辞任をされて、着手金も返ってこないという事態になりかねません。
借金を免除してもらうためには、ご自身でも努力することが必要なのです。
その覚悟さえあれば、手続自体は専門家に任せていれば問題ありません。
一人で悩まずに、まずは専門家に相談しましょう。