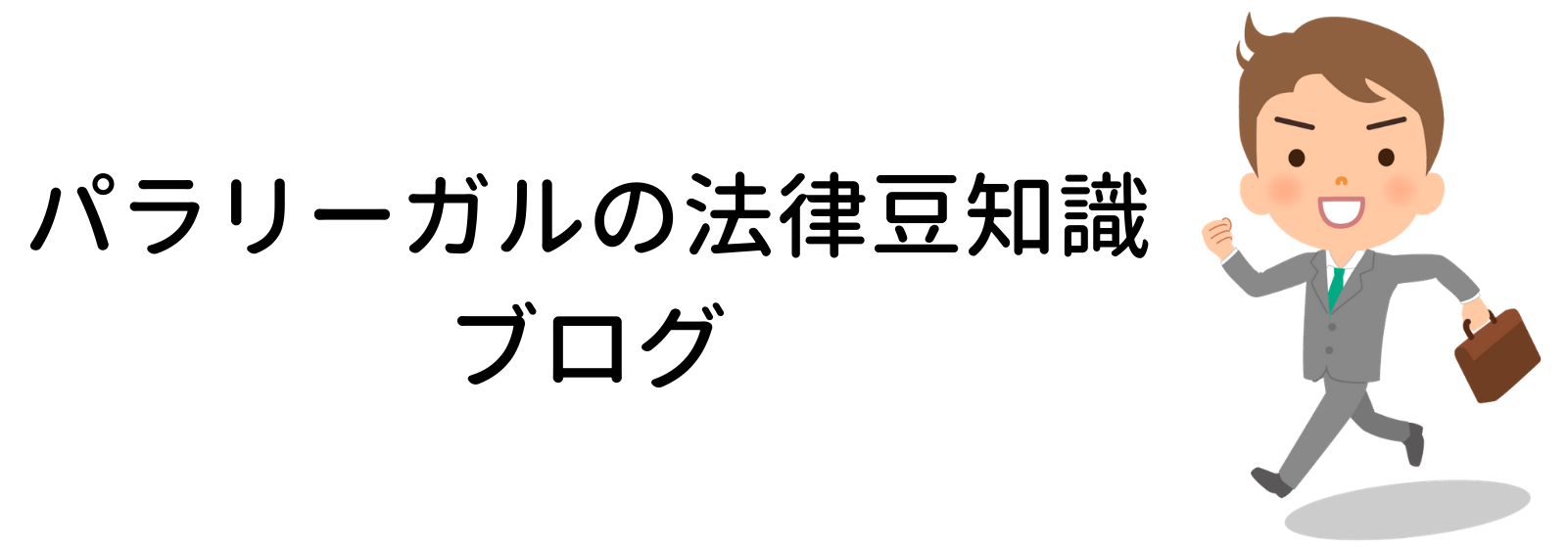どうも、マサトです。
以前、債務整理をする人が増えているというお話をしました。
借金を整理することが債務整理の目的ですが、手続を進めていくとラッキーなことが起こったりします。
過払金です。
皆さんは、過払金って知っていますか?
最近は、テレビCMでも流れているので、知っている人も多いかと思います。
過払金は、一言でいうと業者から返してもらえるお金のことです。
一時は、相当な件数の過払金が発生し、そのせいで倒産してしまった企業もあります。
それでは、過払金とはどんなお金のことで、どのような流れで返ってくるのでしょうか。
「過払金ってそもそもなに?」
「過払金っていくらくらい返ってくるの?」
そういった疑問をお持ちの方も多いかと思います。
本日は、過払金について解説いたします。
過払金が発生する仕組み
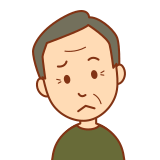
過払金ってなんで発生するの?

グレーゾーン金利が撤廃されたからです。
過払金が発生する仕組みは、グレーゾーン金利です。
グレーゾーン金利が何かというと、出資法という法律と利息制限法という法律の狭間のことになります。
グレーゾーン金利
過去の出資法では、利率の上限が29.2%と決まっていて、これを超えると刑事罰を受けてしまうのです。
そして、利率を定めた法律にもう一つ利息制限法というのもがあったのですが、こちらの上限は15%から20%と決まっていました。
しかし、罰則がなかったのです。
なので、業者は罰則を受けないギリギリの29.2%で貸し付けを行っていたのですね。
この15%から20%と29.2%の間のことを、グレーゾーン金利といいます。
貸金業法の改正
しかし、貸金業法が改正され、出資法の上限も20%となったのです。
それにより、これまで20%以上で返済していた分は払いすぎているのだから、借りていた人に返しなさいとなったのが、過払金です。
これまで、20%以上の利率で借りてたことがある人は、過払金が発生している可能性が高いということですね。
まずは引き直し計算で金額を確定
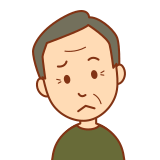
過払金がどれくらい発生しているのかはどうやって調べるの?

業者から取引履歴を取り寄せて、引き直し計算を行います。
過払金がいくら発生しているのかは、計算してみないとわかりません。
専用の計算シートに入力して、過払金を計算します。
債権調査までの流れを知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
ちなみに、過払金は原則キャッシングの借入でしか発生しません。
ショッピングなどの場合は、もともと利率が低く設定されているからです。
また、銀行のカードローンなども利率が低く設定されているので、原則過払金が発生することはありません。
業者側で計算してくれる場合もあるのですが、業者の計算には利息が付いていません。
過払金にも利息が付くのです。
5%ではありますが、長期間の取引があるとそれだけで何十万円もの差が出ることもあります。
なので、業者が計算していたとしても、必ず計算をし直します。
過払金請求通知を送って過払金を請求
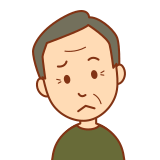
計算が終わったらどういう流れで進むのですか?

計算して出た金額を、業者に返還するよう請求します。
まずは計算結果をお客さんに伝え、いくら回収したいのか希望をお伺いします。
その希望を大前提とし、業者と話をしていくことになります。
請求通知の発送
まずは、書面で請求通知を発送します。
いつからいつまでの借入で、過払金がこれくらい発生しているので、返還してください、という内容のものです。
業者が確認したら、連絡がきます。
注意点
当然ではありますが、過去に請求して和解している場合は返還されません。
たまに、お客様も和解したことを忘れてしまい、また依頼してしまうということが発生します。
また、時効にかかっている場合も返還してもらえません。
過払金の時効は、最終取引日から10年となっています。
この期間を過ぎると、原則返還してもらえないので注意してください。
和解交渉で金額を確定
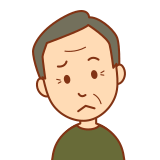
業者とは、どのように交渉が進んでいくんですか?

お互いの希望金額を伝えて、納得いくまで話し合いをします。
請求通知を送ると、業者から連絡がきていくら返せるのかを伝えてくれます。
その金額が、お客様の希望以上であればすぐに和解となります。
希望の金額以下であれば、またこちらから希望金額を伝えます。
その繰り返しです。
回収方法には、2通りの方法があります。
任意交渉
話し合いで解決するのが、任意交渉です。
発生した過払金の満額を返還してくれる業者は稀です。
大体は、5割から8割くらいの金額に落ち着きます。
業者と折り合いがつけば、和解成立となります。
もし、希望する金額に届かない場合は、訴訟を提起することになります。
任意交渉のメリットは、解決が早いことです。
デメリットは、金額が低くなりがちなところです。
訴訟提起
話し合いで決着がつかない場合、または最初から満額を回収したいという場合は、裁判所に訴訟を提起します。
判決を得れば、強制執行を行うこともできますが、最終的には話し合いで解決になることがほとんです。
訴訟提起の場合は、最終的に話し合いになったとしても、任意交渉よりも多く回収できる可能性が高いことがメリットです。
デメリットは、時間と費用がかかります。
解決に1年くらいかかることも、多々あります。
注意点
争点と呼ばれるものがあります。
例えば、一度完済してから次に借りるまでに何年も空白期間がある、その期間に解約してしまっている、などの事情です。
そういった事情があると、過払金の金額に大きな影響を与えてしまいます。
専門的な話になってしまうので、簡単にご説明しますと、何年も空白期間があるとそこで一度取引が終わっていると判断されてしまうことがあるのです。
そうすると、先ほどお伝えした時効の問題で、過払金が消滅してしまいます。
取引が終わっていると判断するのか、それとも続いていると判断するのか、それが争点と呼ばれるものです。
争点があると、業者との話し合いが長引くことが多く、解決までに時間がかかります。
また、任意交渉では話し合いにならず、訴訟提起するしかないというケースもあります。
争点については、専門家からも面談の時などに聞かれると思いますので、その時に伝えておいてください。
数か月で業者から返金
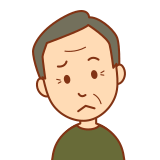
返金までにはどれくらいかかるんですか?

任意交渉なら、請求から6か月くらい、訴訟なら請求から1年くらいとなります。
和解が完了すると、あとは業者からの入金を待つのみです。
手続全体の期間でいうと、任意交渉の場合は最低でも半年はみたほうがいいです。
それより早くなることもありますが、業者によって返還時期が全く違うので、平均すると半年くらいになってしまいます。
訴訟の場合は、1年はみたいですね。
返金された後は、専門家の報酬やかかった実費などを差し引いて、2週間以内くらいには入金してくれます。
これで、手続自体は完了です。
過払金の費用
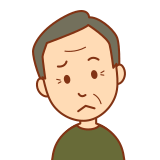
過払金の費用はどれくらいかかりますか?

依頼する専門家によって違いますが、返還額によって変動します。
費用は、依頼する専門家によって変わりますが、ほぼ同じ金額です。
固定の費用
1件当たり、必ずかかるものです。
着手金 0円~2万円
成功報酬
固定 2万円
任意交渉 回収した金額の20%
訴訟提起 回収した金額の25%
減額報酬 減額した分(0円まで)の10%
例を出して説明します。
現在の借金額が100万円あるとします。
引き直し計算をした結果、200万円の過払金がありました。
任意交渉により、150万円を回収したとします。
この場合、
着手金 2万円
成功報酬 固定 2万円
20% 30万円(150万円×20%)
減額報酬 10% 10万円(100万円×10%)
合計 44万円
費用は44万円となるので、150万円から44万円を差し引いて、106万円がお客様の手元に残ります。
もし、訴訟で回収したとなれば、印紙などの実費がプラスされます。
また、成功報酬も25%で計算します。
だいたいは、回収した金額から支払うことになるので、事前に費用を払う可能性はほぼないです。
着手金についても、回収した金額から差し引くのが通常となります。
まとめ
過払金についてご説明しました。
昔から借入がある人は、かなりの確率で発生しているかと思います。
取引期間が長いと、それだけ金額も大きくなるので、場合によっては過払金で他の借金をすべて返済できたりもします。
過払金は、債務整理のどの方法を選択しても発生する可能性があります。
債務整理の方法を知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
一時でも、利率20%以上で借入をしていたことがある人は、過払金が出ているかどうかを調べてみてもいいかもしれません。
調査だけなら、無料でやっている専門家もいますので、依頼してみてはいかがでしょうか。
回収できる過払金の金額は、依頼する事務所によっても変わってくるので、過払金の回収実績のある事務所に依頼するようにしましょう。
今すぐにできるだけ多くの過払金を回収したい方は、こちらの記事をお読みください。