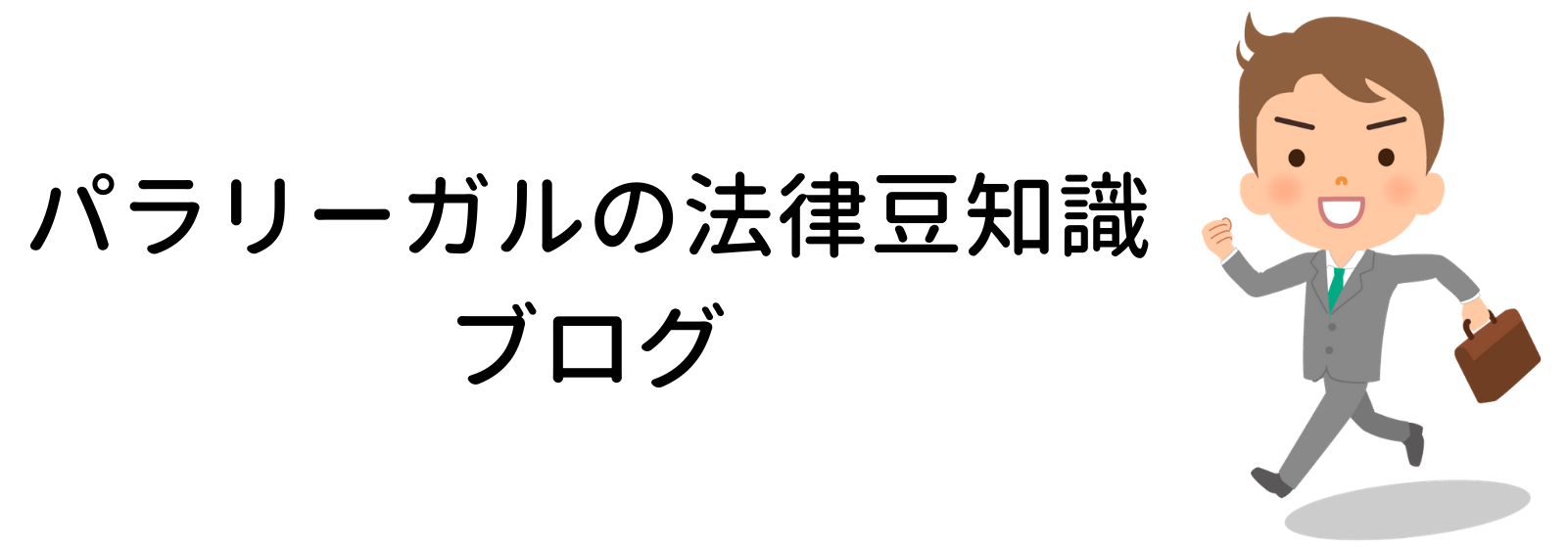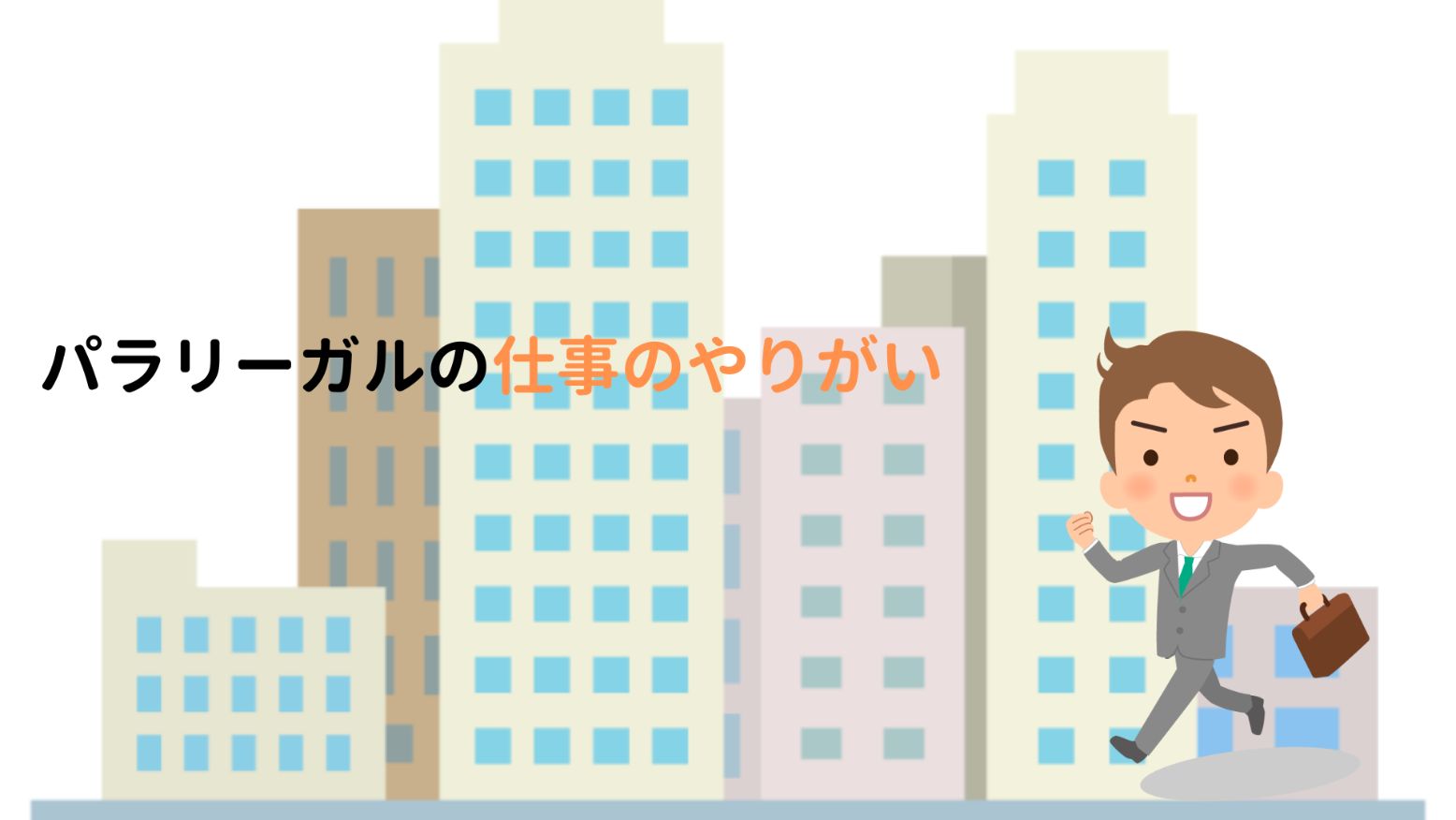マサトです。
相続財産の中でも、最も価値が大きくなるものの一つが不動産です。
相続登記は、必ずしもしなくてはいけないわけではありません。
しかし、放置しておくと後々手続が面倒になるので、早い段階で対応しておくに越したことはありません。
本日は、相続登記の手続についてお話しします。
「相続登記は、簡単にできますか?」
「相続登記をしないと、どんなデメリットがありますか?」
相続登記の手続は、そこまで難しくありません。
私自身も、親族の相続登記を自分でやったことがあります。
ただ、ゼロから調べながらやるのは、正直大変です。
本記事では、相続登記のやり方を簡単に解説します。
自分でやってみようと思っている方は、参考にしてください。
難しそうだなと感じたら、司法書士に依頼しましょう。
相続登記とは

相続登記は、必ずしないといけないですか?

義務ではありませんが、後々面倒になるので早めに手続をしましょう。
相続登記とは、被相続人から不動産を相続した際に、登記名義を変更するために行う手続です。
相続財産に不動産がある場合は、必ず発生します。
ただ、冒頭にお伝えした通り登記義務があるわけではありません。
相続登記をしなかったとしても、罰せられることはないです。
しかし、相続登記をしないと後々面倒なことになります。
まず、相続登記をしないままでいると、その不動産を売却することができません。
登記上の所有者が亡くなった方のままですから、当然といえば当然です。
そして、相続登記しないままの状態でいると、相続人が亡くなってしまうこともあります。
そうなると、さらに登記が複雑になってしまうのです。
相続登記を放置しても、メリットは何一つないので、できるだけ早い段階で相続登記の手続を行ったほうがいいでしょう。
それでは、以下簡単にやり方をご説明します。
複雑なケースは、自分でやるのは難しいと思いますので、単純なケースを前提としてお話しします。
複雑なケースは、登記の専門家である司法書士に相談したほうが良いです。
まずは対象不動産の特定

名寄帳まで調べたほうがいいですか?

生前、亡くなった方から所有している不動産についてすべて聞いていれば、確認しなくても問題はありません。
まずは、相続財産である不動産を特定します。
通常は、自宅のみであることがほとんどでしょう。
もし、自宅以外にも不動産があるかもしれないという場合は、固定資産税の課税明細書を確認してみてください。
そこに、亡くなった方の所有する不動産がすべて記載されています。
課税明細書がない場合は、名寄帳というものを役所で取れば確認が可能です。
ここでは、自宅のみであるという前提で、進めさせていただきます。
自宅の登記簿を取得してください。
法務局で、地番や家屋番号などを申請書に記入して取得します。
もし、地番や家屋番号がわからなくても、住所がわかっていれば法務局で地番や家屋番号を調べてくれるので、心配はいりません。
登記簿を取得したら、被相続人の名前や住所に変更がないかを確認してください。
最も大変な作業である相続人調査

相続人調査は、自分でもできますか?

誰が相続人になるのかは、民法の知識がないと難しいかもしれません。
別の記事でも書きましたが、相続が発生すると必ず相続人調査が必要になります。
相続人が誰かを確定しないと、相続手続自体が進まないからです。
相続登記をする際にも、相続人の調査は必須です。
具体的にどうするかというと、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて取得します。
この作業が、最も大変です。
戸籍には、どこの戸籍から移ってきたのかが記載されています。
それを辿っていくのですが、昔になればなるほど戸籍が見づらくなります。
なぜなら、昔の戸籍は手書きで書いてあったりするのです。
また、被相続人の年齢が高いほど、辿る戸籍の数も増える可能性が高いです。
ただ、簡単な場合はあっという間に終わります。
生まれて親の戸籍に入り、結婚して新しい戸籍を作って亡くなったという場合は、2つの戸籍だけ取得すればいいということです。
ただ、こんな極端なケースはほとんどないので、ある程度調査に手間がかかると考えてください。
必要書類の収集

必要書類は、相続の方法によって全く違うのですか?

基本的な書類は同じで、一部異なっています。
基本的な必要書類は変わりませんが、相続の方法によって必要書類が異なります。
相続の方法ごとに、必要書類をご説明します。
法定相続分で相続する場合
相続人が一人だけの場合は、最も簡単な方法です。
相続人が複数いる場合は、法定相続分で相続することはあまりおすすめできません。
共有になってしまうからです。
共有すると、後々面倒になる可能性があるのです。
詳しくは、こちらの記事を読みください。
できれば、遺産分割協議をして一人に絞ったほうが、後々のためになります。
必要書類は、以下の通りです。
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 相続人全員の戸籍
遺言書通りに相続する場合
遺言書通りに相続する場合も、比較的簡単です。
特に、公正証書遺言であれば検認の手続が不要なので、非常にスムーズに進められます。
公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がありますので、注意してください。
遺言書について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
必要書類は以下の通りです。
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 相続人全員の戸籍
- 遺言書
遺産分割協議をして相続する場合
遺産分割協議をする場合は、最終的に遺産分割協議書を作成して相続人全員の実印を押印する必要があります。
また、相続人全員の印鑑証明書の提出も必要です。
若干、他よりも作業が多くなります。
必要書類は、以下の通りです。
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 相続人全員の戸籍
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
書類が整ったら法務局に申請書等を提出

申請書を提出するのは、法務局に出向く必要がありますか?

郵送やオンラインでも可能ですが、自分でやるなら法務局に行ったほうが確実です。
必要書類がそろったら、申請書を作成して法務局に必要書類と一緒に提出します。
申請書は法務局のHPからダウンロードが可能です。
記載例もあるので、それを参考に作成してみてください。
その際に、登記後原本を返してもらいたい場合は原本還付の書類も一緒に提出します。
提出の方法は、法務局に直接持っていくか、郵送になります。
オンラインでの申請も可能ですが、今後登記を何件も申請することがない限り、このためだけにソフトをダウンロードする必要はないと思います。
結構手間がかかるので。
直接持っていくのが、最も確実な方法です。
不備があれば、その場で教えてくれますし、印紙なども法務局で買ってそのまま提出できます。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。
これを、印紙で購入し申請書に張り付けて提出します。
郵送の場合は、不備があったときに法務局に行かなくてはならないので、二度手間になる可能性が高いです。
自分でやるのであれば、法務局に出向いて手続をしたほうが間違いありません。
まとめ
相続登記のやり方を、簡単にご説明しました。
私個人の意見としては、司法書士に依頼したほうがいいです。
相続登記が複雑なものかどうかを判断するのは難しいですし、自分で調べながらやるのは結構な時間がかかります。
普段から法律業務を行っていれば、相続人調査などもスムーズにできますが、ゼロから調べながら調査するのは大変です。
また、それが合っているかどうかを提出するまで確かめようがありません。
司法書士に依頼した場合は、5万円から10万円ほどの費用が掛かりますが、手間暇を考えたら十分に価値があると思います。
難しそうだなと思ったら、無理せずに司法書士に依頼するようにしましょう。