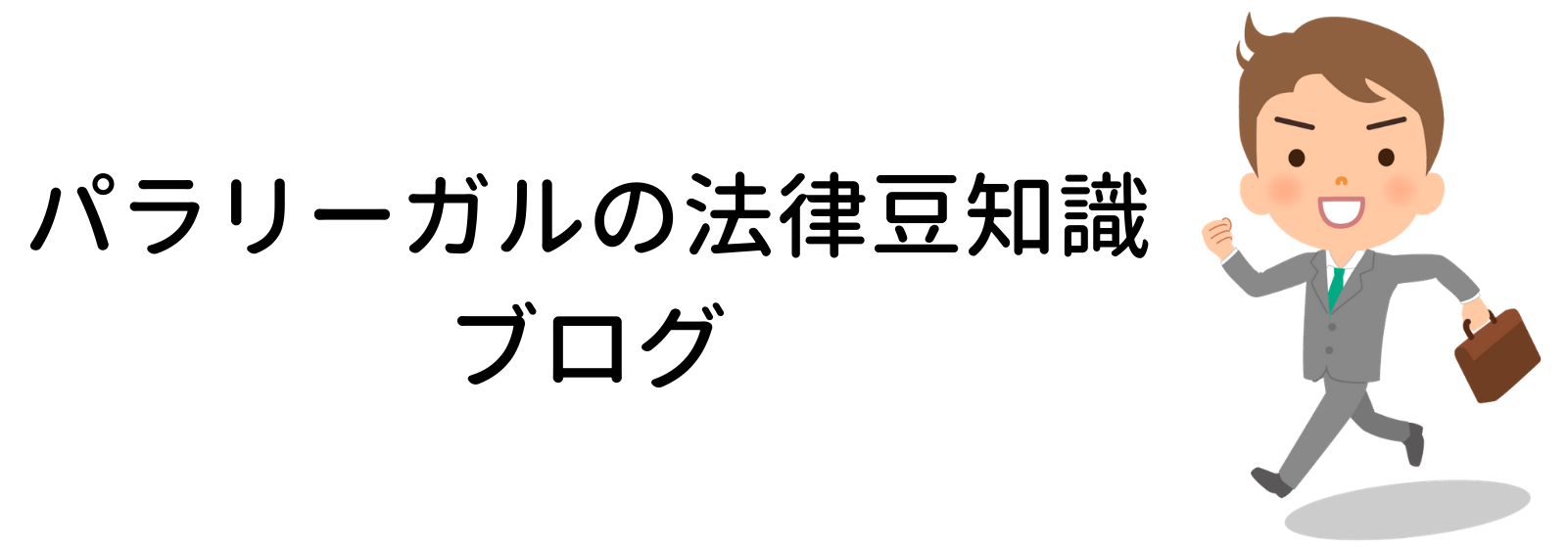マサトです。
被相続人がお亡くなりになると、お金が必要になります。
お葬式ですね。
それ以外にも、日々の支払いなどがあるはずです。
被相続人以外の方がお金を管理していれば特に心配はないですが、被相続人の方がお金を管理している場合は、口座から引き出せなくなってしまいます。
本日は、被相続人がお亡くなりになったあとの預貯金についてお話しします。
「遺産分割が終了するまで預貯金がおろせないって本当ですか?」
「相続人であっても、1円もおろせないんですか?」
以前は、被相続人がお亡くなりになると口座が凍結され、相続人であっても遺産分割が完了するまでは、預貯金がおろすことができませんでした。
しかし、民法が改正されてこの問題は解決されました。
本記事では、改正された内容についてご説明します。
被相続人が亡くなった後の預貯金について知りたい方は、参考にしてください。
これまでの相続発生後の預貯金の取り扱い

遺産分割が完了するまで預貯金がおろせないって、本当ですか?

これまでは確かにおろせませんでしたが、民法改正により可能となりました。
これまでは、被相続がお亡くなりになった後に共同相続人が単独で預貯金を引き出すことができませんでした。
当然と言えば当然です。
相続人が単独で引き出すことができてしまっては、一部の相続人に相続財産を勝手に使われてしまい、適正な相続がすることができなくなってしまいます。
しかし、お葬式の費用や日々の支払いなどもしなければなりません。
遺産分割を早々にすればいいのですが、そんな簡単に家族での話し合いが済むわけはありません。
相続人にとっては、非常に困る状況だったわけです。
金融機関に被相続人の死亡が発覚する前に、全て預貯金をおろしておくということが当たり前でした。
預貯金の払戻制度の創設

いつからおろせるようになったのですか?

2019年7月1日からとなります。
2019年7月1日から施行されました。
上記のような問題を解決するために、民法が改正されたわけです。
一定の範囲内で、相続人単独での払戻が可能となりました。
これにより、お葬式の費用など必要な支払いに対応できることになったのです。
では、どの範囲まで払い戻しが認められているのでしょうか。
預貯金の払戻制度の内容

払戻金額に上限はないのですか?

一定の範囲までと決まっています。
払戻が認められる範囲は決まっています。
相続発生時の預貯金額×3分の1×法定相続分です。
例えば、預貯金額が600万円、被相続人が亡くなり妻と子が相続人だとします。
妻が払戻できる金額は、600万円×3分の1×2分の1で、100万円ということです。
法定相続分については、こちらの記事をお読みください。
家庭裁判所の許可も、他の相続人の許可も必要ありません。
ちなみに、150万円が限度となっています。
預貯金の払戻制度の方法

払戻は、どうやって行えばいいのですか?

金融機関に書類を提出して行います。
金融機関に対して、自分が相続人であることを証明する必要があります。
したがって、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、自身の本人確認書類が必要になります。
手間はかかりますが、必要な現金をいち早く用意できるようになったことは、非常に大きなメリットだと思います。
注意点としては、金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので、まずは金融機関に必要書類について問い合わせをしてから、書類を用意するようにしましょう。
まとめ
いかがでしょう。
これまでは、遺産分割が完了するまで全く引き出せなかった預貯金が、単独で引き出せるようになるということは、非常に大きなことです。
被相続人が亡くなって、さあお葬式の費用を用意しようと思っても口座からお金が引き出せない。
当然焦りますよね。
今後は、そういった心配をする必要はありません。
ただ、書類は必要になりますのでお気を付けください。