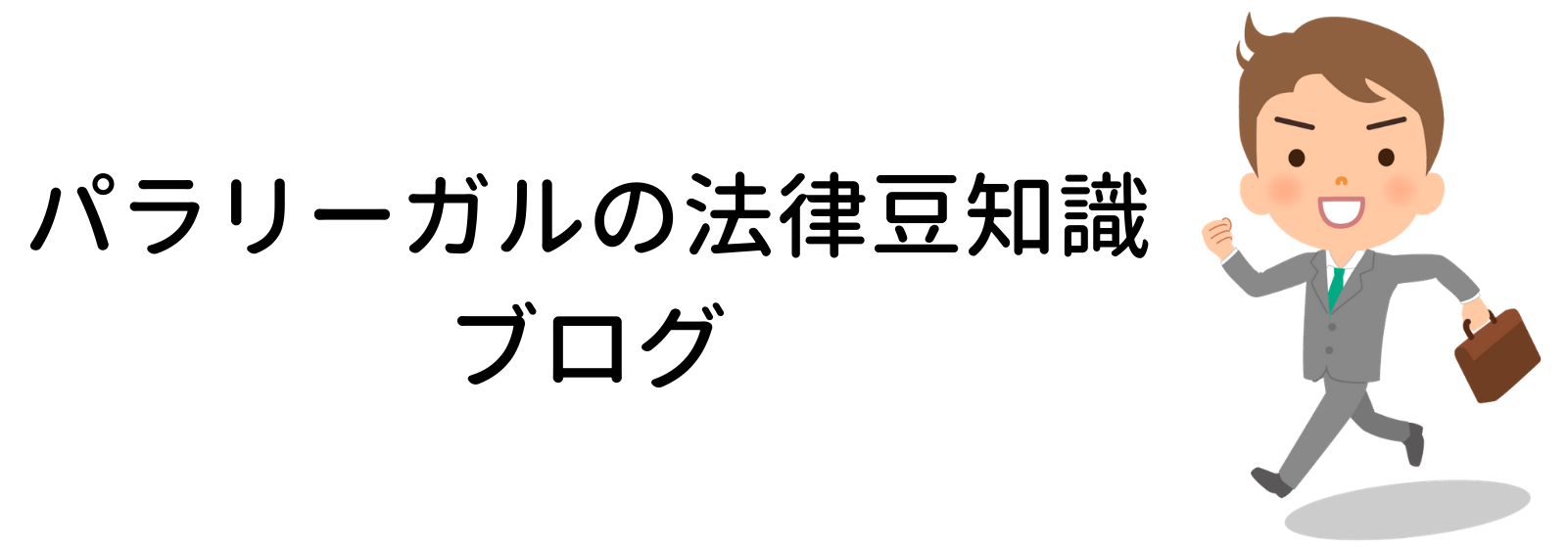マサトです。
相続財産には、不動産や現金などがあります。
では、生命保険の死亡保険金は相続財産に含まれるのでしょうか。
最近は、色々な保険が出てきており、ネットなどで簡単に入れるし保険料も安いということで、保険に入る人も増えています。
本日は、相続における死亡保険金の取り扱いについてお話しします。
「生命保険の死亡保険金って、相続財産に含まれるの?」
「含まれないとしたら、全額受取人がもらえるの?」
結論から言うと、生命保険の死亡保険金は相続財産には含まれません。
受取人固有の財産となるため、受取人がそのままもらえます。
本記事では、生命保険の死亡保険金が相続でどのような取扱となるのかについて、解説します。
保険金について理解し、正しい相続手続をするための参考にしてください。
死亡保険金は原則相続財産ではない

死亡保険金は、相続財産ではないんですね?

その通りです。したがって、遺産分割の対象にはなりません。
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。
したがって、遺産分割の対象にはなりません。
誰が保険金を受け取るのかを、相続人間で話し合う必要はないということです。
もし、受取人が相続放棄をしていても、保険金は相続財産ではないので問題なく受け取ることができます。
相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
ただし、場合によっては特別受益の持ち戻しの対象となる可能性がある点は注意が必要です。
特別受益とは、一部の相続人が遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことをいいます。
生命保険の死亡保険金は、この特別受益に該当はしないのですが、特別受益の規定が準用される可能性はあるのです。
例えば、相続財産が全くなく相続人は全く財産を引き継げない時に、これまで全く家に寄り付かなかった末っ子の三男が生命保険の死亡保険金1億円の受取人になっていたとしたら、他の相続人はどう思いますか?
間違いなく、納得できないですよね。
そういった場合に、1億円を相続財産に持ち戻して、改めて相続人間で分け合うのが特別受益の持ち戻しです。
最終的な判断は裁判所がすることになるので、持ち戻しになるかどうかは何とも言えません。
まずは、弁護士に相談してみましょう。
死亡保険金の受取人が重要

受取人が、被相続人自身になっていた場合はどうなるのですか?

法定相続人が受取人になるであろうという、黙示の意思表示あると解釈され、法定相続人が受取人になります。
生命保険の死亡保険金は相続財産ではありませんが、受取人によっては保険金を分ける場合もあります。
以下、ケースごとに見ていきます。
受取人が被相続人
自分の保険金を自分が受け取る場合です。
この場合、被相続人の意思として、法定相続人を受取人とするであろうと解釈されます。
したがって、法定相続人が受取人となります。
この場合は、法定相続分で分けることになります。
法定相続分について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
受取人が特定の相続人
特定の相続人が、保険金を受け取れます。
1人でも2人でも、特定されていれば受取人になれます。
特別受益の持ち戻しのリスクはありますが、該当しなければ問題ありません。
受取人が法定相続人
受取人が、法定相続人と指定されている場合は、法定相続分で法定相続人が受取人となります。
相続財産ではありませんが、この場合は相続財産と同じように配分されます。
受取人が指定されていない
受取人が指定されていない場合は、法定相続人が受取人となります。
この際に注意が必要なのは、法定相続分で受け取るわけではないという点です。
保険金は、相続財産ではないからです。
保険の約款によりますが、通常は按分されます。
3人いれば、相続人がどんな組み合わせだろうと、3等分ということです。
受取人が既に死亡していた場合
受取人が死亡していた場合は、その受取人の法定相続人が受取人になります。
保険金は、受取人の固有の財産となるので、既に死亡している場合は受取人の相続財産になるということですね。
この場合も、法定相続分ではなく按分となるのが通常です。
死亡保険金の税法上の取扱とは

税金の面でも、相続は関係ないのですか?

税法上は、取り扱いが異なります。保険金は、みなし相続財産となるのです。
ここまで、相続における保険金の取り扱いをみてきました。
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。
しかし、税法上は取り扱いが別となります。
どういうことかというと、みなし相続財産として取り扱われるのです。
被保険者、契約者、保険金の受取人によって、課税関係が全く変わってきます。
相続税に関しては、また別の機会にお話しします。
まとめ
生命保険の死亡保険金は、相続財産ではないということを忘れないでください。
もし、自分が受取人になっていて、他の相続人から相続財産だから遺産分割で話し合おうと言われても、対応する必要はありません。
あくまでも、あなたの財産ですから。
もっとも、相続人同士の関係性を考えたら、無下に突っぱねてしまうのは良くないでしょう。
不公平感が大きい場合は、なにがしかの対応をしてあげたほうがいいかもしれません。