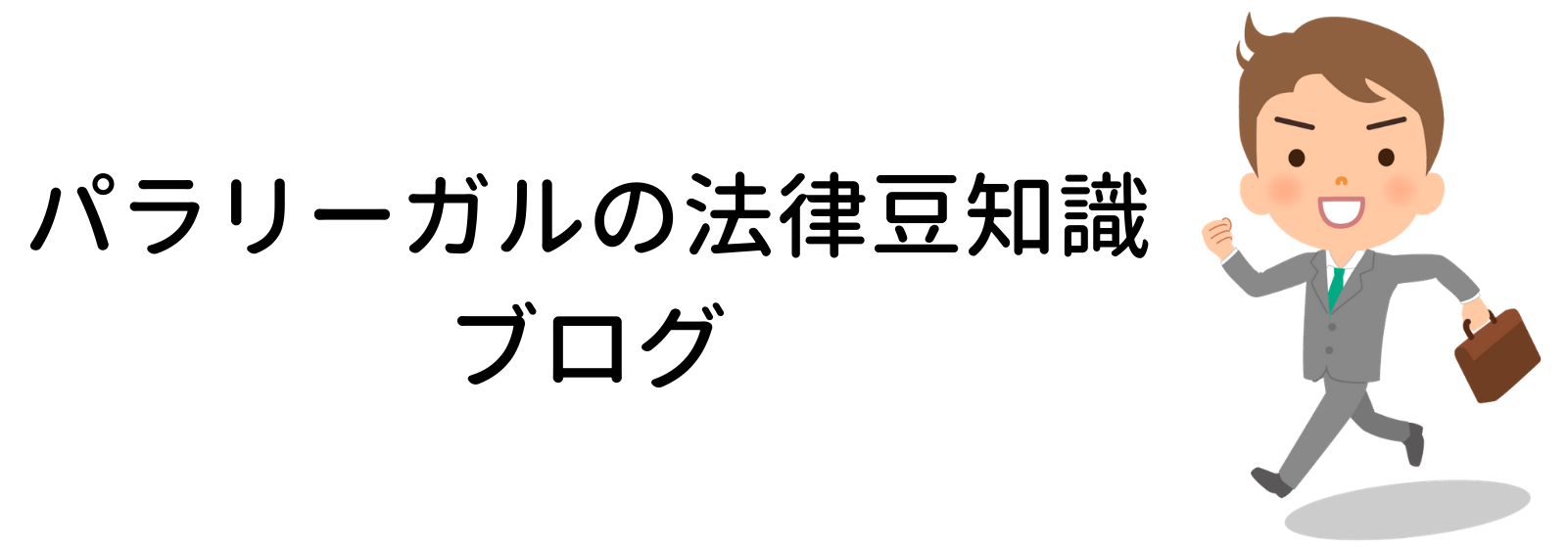マサトです。
相続は、財産を引き継ぐというイメージを持たれている方が多いと思います。
確かに、財産を引き継ぐということに間違いはないのですが、現金や不動産などのプラスの財産だけを引き継ぐわけではありません。
マイナスの財産も引き継ぐのです。
では、マイナスの財産のほうが多かった場合はどうすればいいのか。
本日は、相続放棄についてお話しします。
「相続放棄ってどんな手続なの?」
「相続放棄の注意点を教えて。」
相続放棄は、全体の財産がマイナスのときに行うのが通常です。
わざわざ、借金を相続しようとは思わないですよね?
相続放棄の手続自体は比較的簡単です。
しかし、相続放棄をすべきかどうかは、専門的な知識が必要になります。
本日は、相続放棄の手続について解説します。
相続放棄を自分でするのか、弁護士に依頼するのか、ご判断の参考になればと思います。
相続放棄とは

相続放棄って、どんな時にするんですか?

相続財産がマイナスになっているときに行います。
相続放棄とは、亡くなった方の財産や権利を一切引き継ぎませんという手続きです。
財産の中には、現金や不動産といったプラスの財産と借金などのマイナスの財産がありますが、相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。
したがって、通常は全体でマイナスになる場合に利用する手続となります。
相続放棄をせずに財産を引き継ぐ場合は、単純承認と限定承認という方法があります。
単純承認とは、全ての財産と権利を引き継ぐことです。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もですね。
特別な手続は不要で、相続が発生して何もしなければ単純承認したとみなされます。
限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐことです。
例えば、プラスの財産が1000万円あったとしたら、債務がいくらあっても1000万円まで負担すればいいよということです。
プラスマイナスでゼロになるということですね。
限定承認は手続が煩雑なので、実際に利用されるケースはあまりありません。
相続放棄の期間は原則3か月

相続放棄をするタイミングは、いつでもいいんですか?

法律で期間が定められており、相続開始を知った時から3か月以内です。
相続放棄をすることができる期間は、法律で決まっています。
相続開始があったことを知ってから、3か月以内です。
つまり、亡くなったことを知ってから3か月以内ということですね。
亡くなったことを知らなければ、期間に算入されません。
この3か月以内という期間は、延長することが可能です。
どんな財産があるのか、プラスなのかマイナスなのかなどを調べるためには、それなりの時間がかかりますよね。
そのような場合には、裁判所に期間伸長の申立をして認められれば、期間を伸長することが可能となっています。
自分でやれば相続放棄の費用は数千円

相続放棄の費用は、どれくらいかかるのですか?

自分でする場合は実費だけなので、だいたい5000円くらいになります。
相続放棄の費用は、実費だけです。
弁護士などに依頼する場合は、その費用もかかります。
実費は、以下の内容です。
- 住民票 300円程度
- 戸籍 1通 450円~700円程度
- 印紙 800円
- 郵券 500円程度
だいたい、3000円~5000円ほどになります。
弁護士などに依頼する場合は、30000円から70000円ほどの費用がかかります。
また、期間の伸長や3か月経過後の相続放棄については、別途費用がかかることが多いです。
相続放棄の手続の流れ

相続放棄の手続は、時間がかかるのですか?

調査に最も時間がかかります。
相続放棄の手続の流れは、以下の通りです。
①相続人と財産の調査をする
②申述書等を裁判所に提出する
③照会書に記入して返送する
④相続放棄受理通知書を受け取る
内容が複雑でなければ、自分でも相続放棄の手続をすることは可能です。
ただ、相続放棄をしたほうがいいのかなどを判断するのが難しいので、弁護士などの専門家に依頼したほうが、間違いはないかと思います。
相続放棄の注意点とは

相続放棄の注意点はありますか?

4つあります。
相続放棄には、いくつか注意点がありますので、気を付けてください。
3か月以内に相続放棄をしないと単純承認となる
相続開始があったことを知ってから3か月が経過すると、単純承認したとみなされて、全財産を相続することになります。
3か月を超えてしまうと、相続放棄が絶対にできなくなるわけではありませんが、難易度が大幅に上がります。
3か月を超えないように、注意してください。
相続人が財産の一部を処分したり隠匿すると単純承認となる
相続財産の一部を何かに使用してしまったり、故意に隠すようなことをすると、単純承認とみなされます。
特に、現金などを使用してしまうケースが多いので、注意してください。
相続放棄をすると次順位の相続人に相続権がうつる
自分が相続放棄をすると、亡くなった方の子や親、兄弟姉妹に相続権がうつります。
つまり、自分以外の相続人の方が全員相続放棄をしなくてはいけないのです。
もし相続放棄をするのであれば、親族間で情報共有をすることが必要になります。
誰に相続権があるのかは専門的な知識が必要になるので、弁護士などに依頼するのが間違いありません。
借金があった場合、過払いになっているかもしれない
消費者金融や信販会社などからの借入は、過払いが出ている可能性があります。
過払が出ているのかを知るためには、取引履歴を取り寄せて計算をしなくてはなりません。
もしそういった借金があることがわかったら、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
過払金と相続の関係について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
まとめ
相続放棄手続について、簡単にご説明しました。
相続放棄は、簡単なケースであれば自分でも手続が可能です。
しかし、相続人や財産の調査をするには専門的な知識が必要になります。
また、相続放棄をしたほうがいいのかどうかの判断についても同様です。
弁護士などの専門家に依頼し、ベストな選択をされることをおすすめします。